村上春樹『風の歌を聴け』が描く戦後日本の虚無感 「日本的なるもの」の喪失を描いた透明な文学
川端:で、おそらく、今回の『風の歌を聴け』もそうなるような気がするんです。ただ、春樹の場合、不思議なことに文体とか登場人物の持っている雰囲気みたいなものは時間が経っても思い出すことができます。そういう、スタイルだけが頭に残るってのは、やっぱり村上春樹の巧さなんでしょうね。
村上龍の『限りなく透明に近いブルー』はまだ、閉塞した世の中に対する「破壊願望」とか「脱出願望」みたいなものを描いていました。でも春樹になるとデタッチメントですから、そういうのを止めるわけですよね。別に何かを破壊したりしないし、脱出願望みたいなものはチラリとは出てきますけど、龍の作品ほど煮えたぎってはいない。破壊や脱出を止めてしまうっていうのは、もちろん方向としてはニヒリスト的ですから不健全であるとは言えるものの、村上春樹のこの止め方には清々しいものを感じるところがあって、不思議と嫌な印象はないんです。
なぜ嫌な感じがしないのかと考えてみると、たぶん、当時の若者が本当に持っていたのであろう気分を、正確に描いているように思えるからです。私は80年代には物心が付いてなかったので実際には知らないんですが、「確かにそういう気分になることはありそうだな」と思わせる迫真性がある。
表面的な会話だが不快感がない
川端:もう一つは、さっき柴山さんが「伝達」つまり「コミュニケーション」の問題だと言われて気づいたことなんですが、確かに春樹の作品の登場人物たちの会話を読んでいると、微妙に噛み合わなくてすれ違っていますよね。うまく言えないんですけど、フワフワして、地に足が着かないような人間関係です。
僕が春樹の小説を何作か読んでみて毎回感じるのは、変なたとえですけど、進学や就職がある4月頃の気分がずっと続いていくというような印象です。生活環境が変わったばかりで、深く噛み合った人間関係がまだないし、宙に浮いたような心地でダラダラと時間が流れていくんだけど、春らしくぽかぽか暖かくて不快ではない、というような。
例えば18、9歳で田舎から東京の大学に出てきて、とりあえずまだすることもはっきりせず、地に足が着いていない時期の若者の感覚みたいなものですが、これって人間が繰り返し経験する気分だよなっていうリアリティがあるんです。だから、そのボーッとした感覚に長く留まってしまうと気持ち悪いんですが、人生に付きもののよくある風景という印象だから、嫌な感じはしないんですよね。

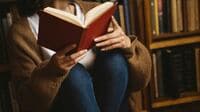































無料会員登録はこちら
ログインはこちら