村上春樹『風の歌を聴け』が描く戦後日本の虚無感 「日本的なるもの」の喪失を描いた透明な文学
川端:そのこととも関係するんですが、春樹は登場人物一人ひとりの、人間としての全体像を描こうとしないイメージもあります。登場人物たちは盛んに何かを喋ってるんですけど、不思議と、その人物のバックグラウンドを読者に想像させないような力が働いていて、「いま喋っているこのセリフ」だけに注意が取られますよね。
その背景でどんな人生を送ってきたのかというようなことはあまり考えさせないような誘導が行われていて、別に悪い意味じゃないんですけど、個々の人物が持っているであろう多面性や歴史性は犠牲にして、特定の側面だけをいくつも繋いでいく形でストーリーが進んでいく。なんか、会話の部分が多いですけど、いきなり話が飛ぶやつも多いじゃないですか。
柴山:そういう飛び方は、なかなかうまいなと思ったんですけど。
川端:これも一種のリアリティですよね。それから、さっきの自殺した彼女の話にしても、自殺の背景の描き込みは全然なくて、わずか数行で死んだ場面の説明が終わる。人物の全体像がないんです。一人の人間が持っている多面的な可能性を、わざわざまとめたりはせずに、一面だけを繋いだような人間関係が描かれているんですが、確かに現代はそういう社会です。
さっき柴山さんが「都市」とおっしゃいましたが、ジンメルの社会学で都市とは「日々出会う人々の大半が顔見知りではないような空間」であると定義されていたように、都市の生活というのは個々の他人の全体像を考えることがないものですよね。そういう意味での都市的な空間の雰囲気が正確に描かれていて、なんか「分かる分かる」って思うのが春樹の小説です。
「相対主義」としての人間関係
浜崎:皆さんが褒めるので、僕一人が孤立しそうですが(笑)、……ただ、先に言っておくと、僕の村上春樹評価というのも、藤井先生と同じで、完全に自分自身の「青春」と密着しているものなので、全く客観的な評価とは言えません。
だから、先に公平を期して言っておくと、皆さんがおっしゃるように、春樹の圧倒的な巧さには頷かざるを得ない。ものすごく実験的なのに、おそらく一度読み出すと止まらないはずです。まさに「都市生活者の自意識」をてこにして読者を物語世界にさらっていく力は並じゃない。
ただ、僕がどこに違和感を持っているのかというと、先ほど言われた「相対主義」とも関係しますが、やっぱり、春樹が決定的な場面で「他者」あるいは「葛藤」を回避しているところなんです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

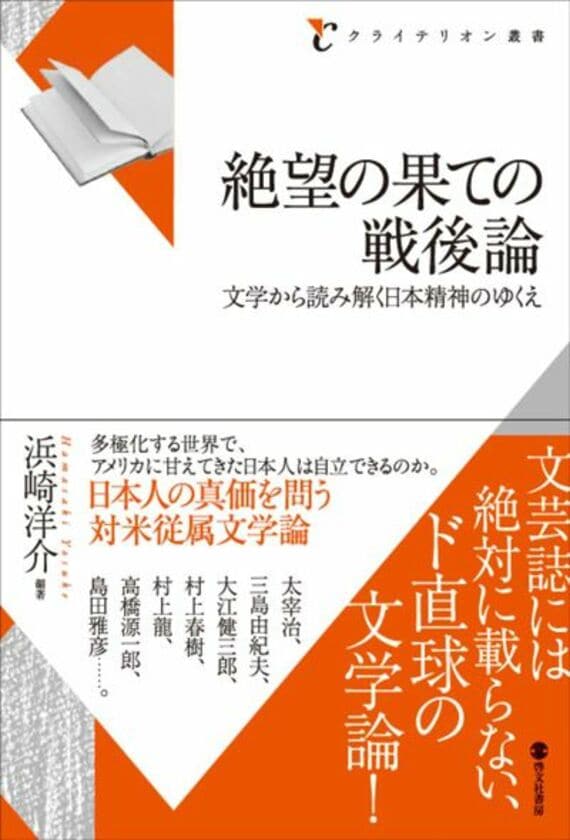
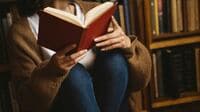































無料会員登録はこちら
ログインはこちら