新規事業立案支援の狙い。
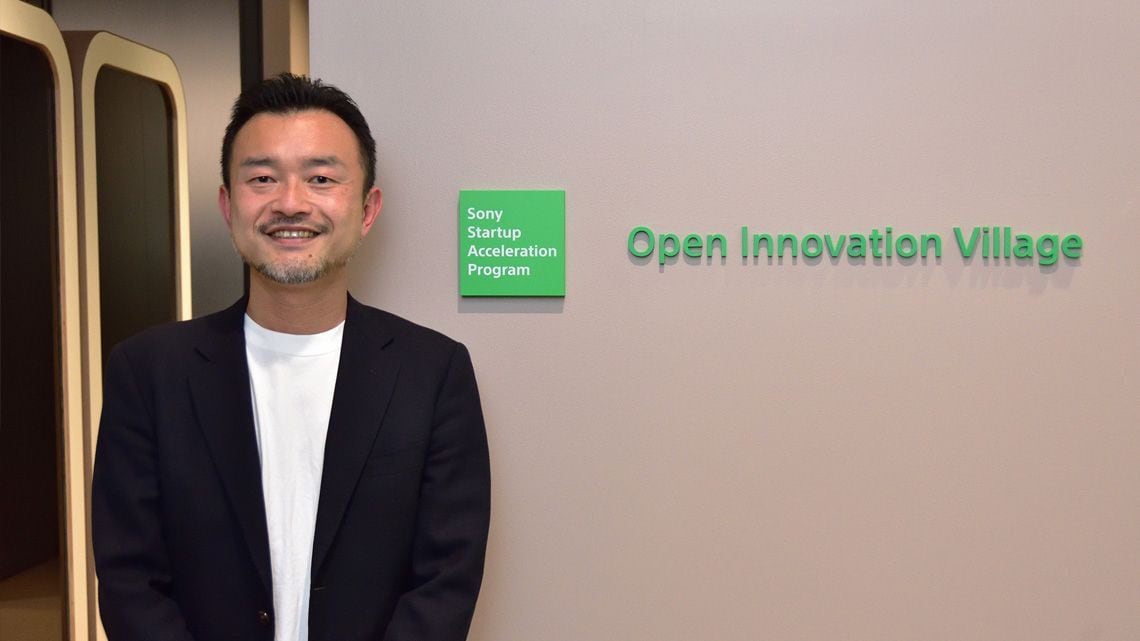
小田島伸至氏は2001年のソニー入社後、海外赴任や事業立ち上げを経験。現在はソニーグループのStartup Acceleration 部門長を務める(写真:記者撮影)
ビジネスモデルを紹介する本や記事は数あれど、体系的に分析した事例はほとんどない。
『週刊東洋経済』2月24日 特大号の特集は「もうけの仕組み 2024年版」だ。四季報記者がユニークなビジネスモデルの会社を解説するとともに、上場企業400社を独自分析した。
![週刊東洋経済 2024年2/24特大号(もうけの仕組み ─2024年版─)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/518nhmVpaVL._SL500_.jpg)
『週刊東洋経済 2024年2/24特大号(もうけの仕組み ─2024年版─)[雑誌]』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。定期購読の申し込みはこちら
「当時のソニーは売り上げが伸び悩み、新たな事業にチャレンジする機会が少なくなってしまっていた」
ソニーグループで10年近く新規事業立案支援を手がけてきた小田島伸至氏はそう振り返る。
今でこそ約1.2兆円の営業利益(2022年度)を稼ぎ出し、時価総額も18兆円以上と日本を代表するエクセレントカンパニーの地位に返り咲いたソニーだが、低収益に苦しんだ時代もあった。
得意としてきたエレクトロニクスの分野でつまずき、スマートフォン事業で巨額の減損を計上したことなどから、13、14年度は連続で最終赤字を経験した。時価総額は2兆円を割ったこともある。
新規事業が減っていることに危機感
「黒字化しても、10年後に自分たちがやっていける事業が乏しい」
トピックボードAD
有料会員限定記事

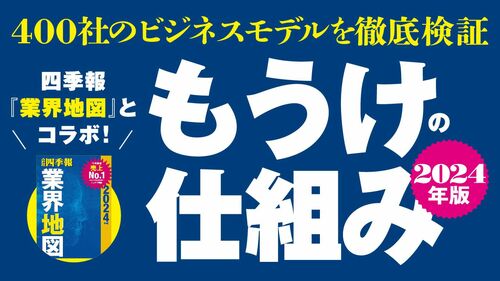
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら