ポイントは「間口」と「奥行き」だ。

![週刊東洋経済 2024年2/24特大号(もうけの仕組み ─2024年版─)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/518nhmVpaVL._SL500_.jpg)
強いビジネスモデルとは何か、まねされないビジネスモデルをどうやってつくるか。「取引の図解」を考案し、ビジネスモデル・デザインや経営戦略論を専門とする井上達彦教授に話を聞いた。
──400社のビジネスモデルの分析結果をどう読み解きますか。
約半分が①の製造販売モデルというのは実感に近い。利益率が低いのも、製品やサービスのよさに頼っているからそれほど儲からないということ。
また、②の流通小売りモデルはつねに価格競争をしているため、収益性が低い。そのことは機関投資家も指摘していた。
製品の販売よりも保守・サービスのほうが利益率は高いため、⑥の設置ベースモデルの利益率が①の製造販売より高いのも想定どおりだ。もし①の会社が⑥の設置ベースモデルに移行すれば、もっと収益性が上がるだろう。
「間口」と「奥行き」を見よ
──⑧のマッチングモデルや⑨の補完財プラットフォームモデルを展開する企業の強さが目立ちます。
強いはずだ。⑧のマッチングは在庫を供給側が持つ。⑨の補完財も自社でやる部分を絞り込めるし、外部のサードパーティーが商品やサービスを供給して価値を高めてくれる。どちらも資本効率がいい。

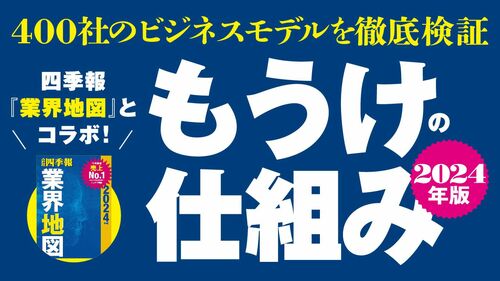

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら