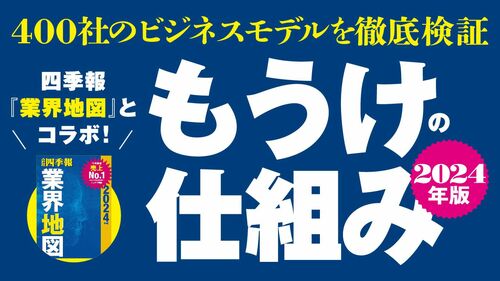損して得取る。

石川地盤のクスリのアオキHD。積極的なM&Aで生鮮食品を強化中だ(写真:記者撮影)
ビジネスモデルを紹介する本や記事は数あれど、体系的に分析した事例はほとんどない。
『週刊東洋経済』2月24日 特大号の特集は「もうけの仕組み 2024年版」だ。四季報記者がユニークなビジネスモデルの会社を解説するとともに、上場企業400社を独自分析した。
![週刊東洋経済 2024年2/24特大号(もうけの仕組み ─2024年版─)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/518nhmVpaVL._SL500_.jpg)
『週刊東洋経済 2024年2/24特大号(もうけの仕組み ─2024年版─)[雑誌]』(東洋経済新報社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。定期購読の申し込みはこちら
ドラッグストア|ウエルシアやアオキが食品を売るのはなぜ?
食品の安売りで集客し、利益率の高い医薬品や化粧品を「ついで買い」させて稼ぐ──。それがドラッグストアの定石だ。
業界最大手のウエルシアホールディングス(HD)の場合、売上高の構成比率は食品が22.2%と最も高い。ただ、売上総利益(粗利)構成比率は13.4%。医薬品や調剤の約半分にすぎない。粗利を削ってでも、即席麺や飲料などの食品を値下げしているからだ。
それでも2023年2月期の営業利益率は3.9%で、一般的な食品スーパーより高い。粗利率が3〜4割程度の医薬品や化粧品、調剤がもうけの源泉となっている。同社に限らず、ドラッグストアは調剤薬局を店舗に併設することで、利便性を高めながら高水準の粗利も確保できるという強みがある。
トピックボードAD
有料会員限定記事