そもそも、オルデンバーグが述べる「サードプレイス」は、多くの現代人にとって心地のよいものであるのかを考える必要がある。例えば、常連がみっちり座っていて、彼らが相互に話し続け、また新規の客にも話しかけてくるような居酒屋を、すべての人が居心地がよいと思うかどうか。
もちろん、慣れてくれば楽しいかもしれない。しかし、それに慣れるまでには時間がかかるだろうし、やはり最初のうちは、そうした店には行きにくいだろう。
オルデンバーグの「サードプレイス」の条件に「誰にでも開かれている」という項目があることは既に見た通りだが、実情を考えてみると、そのような場所にふらりと行くのはなかなか難しい、という人も多いのではないだろうか。
「ほどほどに、人とつながれる空間」としてのスタバ
一方で、人間にとって自身が行くべき場所が家庭、つまり「家」か、仕事場しかない、というのも耐えがたいことである。アメリカの社会学者、ロバート・パットナムが明らかにしたように、人と人とのつながりは「社会関係資本」といって、その人間の幸福度を大きく左右する。どこかで、さまざまな人とつながることが重要なのである。
人とつながりたい、しかし、親密すぎるつながりは精神的に負担になる。そんなときにスタバという場所は適度な居場所を人々に与える。そこでは、決して客同士が干渉し合うこともない。
一方で店員との適度なコミュニケーションは担保されている。それはスタバがある意味で「矛盾」した「サードプレイス」を作り上げているからなのだが、こうした「ほどほどに人とつながることのできる空間」は、現代人にとって非常に意味のある空間である。そして、そのような空間を作っていることは、スタバに人を呼び寄せる要因にもなっているだろう。
つまり、ほどほどな「サードプレイス」を求めて、人々はスタバにやってくる……。
これが筆者なりの結論である。
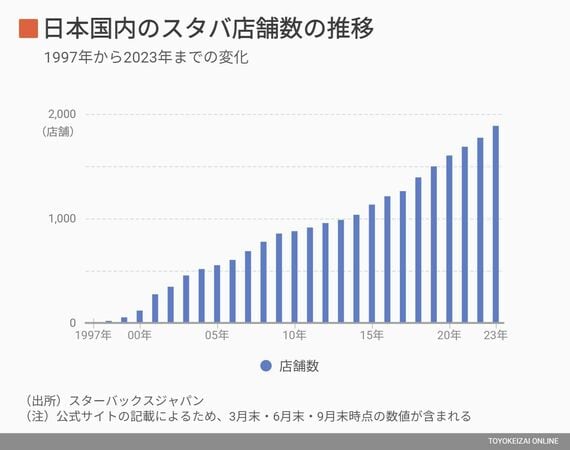































無料会員登録はこちら
ログインはこちら