
マネジャーほど割に合わない役職はない
よいマネジャーとは、人々と仕事を結びつける役割を果たせる人たちだ。ハッキリ目に見える場合ばかりではないが、マネジャーの役割は極めて大きい。
マネジャーは、業務の流れをマネジメントし、メンバーがどこで働くかという方針を示し、メンバーが集中して仕事に取り組む時間を確保しなくてはならない。
勤務スケジュールがメンバーのニーズに適合しているか、メンバーが業務を通してスキルを向上させられるか、すでに持っているスキルを反復的に用いるだけにとどまっていないかといったことにも気を配る。
社員間の公平性について判断し、社員の尊厳を大切にする役割も担う。社員が現在の職でアップスキリングを行ったり、新しい職に移るためのリスキリングに取り組んだりするよう促すことも期待される。
優れたマネジャーが欠かせないことはハッキリしている。しかし、この点はいささか奇妙にも思える。長年にわたり、リーダーにばかり脚光が浴びせられて、マネジャーの存在意義を疑う声すらあったからだ。
マネジャーは、変化にかたくなに抵抗する「永久凍土」のような存在だと揶揄されることも多い。このような状況では、マネジャーが新しい働き方を設計する最前線に立っていないとしても不思議でない。

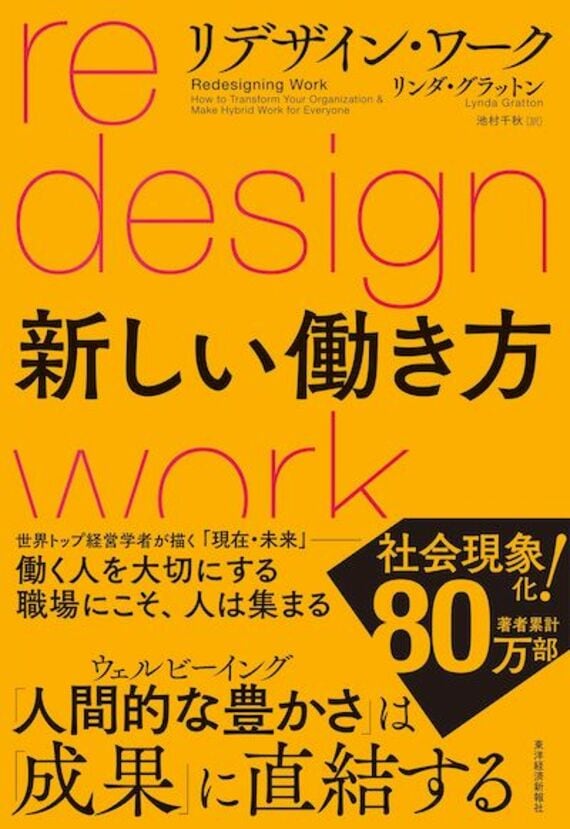
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら