アメリカでの受け入れ病院も決まっていたが、容体は悪化する。補助人工心臓をつけたことでできた血栓が脳の血管を詰まらせ、脳梗塞を発症した。医師からは「脳の機能の4分の3が失われており、脳死に限りなく近い状態でゆっくり心臓が止まっていくのを待つしかない」と伝えられた。
そのときに、両親がすぐに返したのは「ほかの臓器は元気ですか?」という言葉だった。もちろん、優希ちゃんの回復を願っていたため、自分の娘がドナー(臓器提供者)側になることは想定していたわけではない。だが、医師の「もちろん、使えますよ」という言葉を受け、2人は臓器提供をすぐに決めた。
提供に迷いはなかったのか。当初は心臓の移植を受ける側で入院していた優希ちゃん。入院していた病院の医師に「臓器をいただくのは人様の命をいただくこと」と命の大切さを教えてもらっていた。だから「すぐに臓器提供を決められた」と大輔さんは言う。
臓器を取り出す手術までの2日間、家族が集まって最期の時間を過ごした。母親が付き添っての優希ちゃんの入院は100日間に及んだ。
ドナー家族と臓器を受け取った移植者(レシピエント)家族が直接会うことはできないが、日本臓器移植ネットワーク(JOT)を通してもらうサンクスレター(提供者への感謝の手紙)で近況報告を受けた。「元気でいることを知り、とてもうれしい気持ちになった」(大輔さん)。
とはいえ、移植した臓器が優希ちゃんの”分身”という意識はないそうだ。「娘の一部だった臓器が、その人の臓器の一部であるという感覚でしかない。娘は亡くなっている。そこに生はないわけですから、娘だとは思わない」と話した。
家族の猛反対にあった男性
臓器提供のことを「命のリレー」と表現することがあるが、誰かの死の上に成り立つ医療であり、きれいごとでは片づけられない。
親族の猛反対にあったというのは、妻(当時58歳)の臓器(肺、腎臓、膵臓、角膜)を提供することを決めた五十嵐利幸(72)さんだ。
その日、いつもどおりの朝を迎え、夫婦それぞれ会社や待ち合わせの場所へと向かった。お昼ごろ、「妻が運転中に事故を起こし、病院へ運ばれたと連絡が入ったのがすべての始まりだった」と五十嵐さんは振り返る。
病院へ駆けつけると、ICUで外傷もなく静かに眠っている妻と会うことができた。だが、医師から告げられたのは「脳幹部の大量出血で、私たちの力では救命はもう無理です。早くて6時間、体力が持って2~3日の命です……」という言葉だった。事故の直前にくも膜下出血を起こしていたのだ。あまりに突然のことに、「死刑宣告を受けたみたいなものだった」と当時の心境を吐露する。


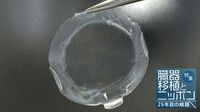





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら