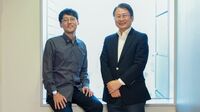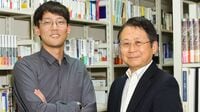「海の帝国」は「陸の帝国」の挑戦を退けられるか 21世紀型「文明の危機」の本質を説き明かす
木村:一度もないのですか。資源輸出で外貨を稼いでいる印象がありますが。
水野:確かに、ロシアは資源の輸出で貿易収支が黒字で、経常収支も黒字を維持しています。経常収支を累計したものが対外純資産(=対外資産マイナス対外負債)となり、経常収支が黒字ですから対外純資産はプラスです。ところが、ロシアの場合、対外資産が生み出す利子・配当受取額よりも対外債務の利子・配当支払い額のほうが上回っているのです。したがって、所得収支は赤字となっています。
1992、1993年の頃は混乱期だったので統計が欠落しているのですが、結局、所得収支赤字が続いているのです。2013年が出超のピークで、そこから所得収支赤字が多少は小さくなりましたが、それでも世界の中では、下から6番目の出来の悪い国ということです。
中国も「海の国」としては劣等国
水野:こんなことを続けていては、いつかアメリカの軍門に下らざるをえなくなるという危機感は高まっていたはずです。近代化の競争の果てに、米ソ冷戦で敗れて、資本主義のルールの下で、エリツィンとプーチンで頑張ってはみたものの、アメリカの相手にはならない。
ならば、ゲームのルールをまったく変えてしまおう。「海の国」のルールでは勝算がないので、元来のロシアである「陸の国」に戻って、領土の拡大を推し進めていこうと、こう考えるのは不思議なことではありません。こうしたことが、ウクライナ侵攻の底流にあったのだと思います。
木村:なるほど。「陸の国」の反逆というか、決起というか。そういう意味では、中国も「陸の国」と捉えるべきですよね。

水野:はい。先の所得収支が、世界でもっとも出超なのが中国です。中国は積極的に外資を導入して発展しているように見えますが、国家としては、高い利潤を外国に支払っている国なのです。一方で、中国が国外で行っている投資、アフリカや東南アジアなどに積極的に投資をしていますけれども、それらはまったく儲かってはいない。
ですから、中国も、俺たちも資本主義には向いてないなと。「世界の工場」などとおだてられていますけども、所得収支の赤字は世界最大ですから、やがて、ロシアと同じように、「海の国」のルールに背を向けて、領土拡張や膨張主義へと舵を切るかもしれません。
木村:ユーラシアの北と南に位置する、ロシアと中国いう2つのメインプレイヤーが、今後、どういった動きをするかは目を離せません。中国とロシアの関係は、手を結び合ったり、牽制し合ったりで、近代以前の清の時代から国境紛争もありましたし、なかなか中ロは一枚岩にはなれないでしょう。
ウクライナとの関係では、中国とウクライナの関係は深い。中国初の空母「遼寧」はウクライナのニコライエフ造船所でつくられて1988年に進水したもので、両国間には軍事的なつながりもある。十数年前には相互で、ウクライナが核攻撃を受けた際には、中国が助けるという条約まで結ばれているわけです。ですから、もしロシアがウクライナに対して戦術核を使った場合、中ロの間には微妙な問題が生じることになります。
ロシアとしては、中国を引き入れて、「中ロ中軸」のような形にしたいのかもしれません。エネルギーでも、軍事技術の提供、武器の提供でも、中ロが強固に手を組んで国際社会の中で存在感を示していく。中ロvs.ほかの国といった、まさに水野先生が言われたような「陸の国」vs.「海の国」の戦いになっていくのか。歴史の転換点と言っても過言ではない、たいへん興味深い時代を迎えていると思いますね。