在宅医療が関わる時期は、往々にして遅れがちです。病院の医師や看護師が在宅医療の実際をあまり知らないがために、「通院できている間は在宅医療はいらない」と言われてしまったり、入院中に「この状態で自宅に戻るのは無理」と言われてしまうことがあります。
また、患者さん本人や家族が終末期であることを認められずに判断を先延ばしにしてしまう場合や、また、自宅に医療者が来ることが嫌だというケースもあります。
しかし「いずれは自宅で」と考えるなら、できるだけ早めに在宅ケアをスタートさせたほうがいいと思います。在宅医療を考えるということは、言い換えれば「終末期」という段階と向き合うことになります。それは多くの人にとって受け入れがたく、避けたいことでしょう。
ですが、残された時間が短くなったときこそ、急に環境を変えることなく、できるだけ落ち着いて過ごしたい人が多いと思います。
その方にとって明日はもうないかもしれないというなかで、慌てて在宅ケアに移行するのも大変なこと。そして残りわずかというタイミングで、在宅医療を支える私たち医師や看護師と「初めまして」という状態になるより、少しでも信頼関係を築けていたほうが安心できると思うのです。
「最後の思い出作り」のサポートも
終末期の患者さんのなかには、余命が限られているからこそ「最後の思い出作りに家族で旅行に行きたい」という人もいます。「最後に家族で豊かな時間を過ごしたい」という願いをかなえるために、私たち在宅医療に関わる医師や看護師も最大限サポートします。
ただ、そうした願いをかなえるには、少しでも元気なうちに動いたほうがいい。判断を先延ばしにすることで、最期の過ごし方の選択肢が狭まるともいえるのです。こうしたことも踏まえ、家で過ごすことを考えるなら、通院できるうちから在宅医と関わることをお勧めします。

がんと新たに診断される人は、年間で約98万人に上ります。このうち15〜39歳のAYA世代と呼ばれる若い世代のがん患者数は約2万人で約2%です。
しかしAYA世代の病気による死亡要因のトップは、がんによるものです。この世代は就学や就労、結婚や出産、育児といった、さまざまなライフイベントが起こる時期。こうしたなかでがんに罹患すると、通学や仕事の継続が困難になったり、治療によって妊娠・出産や育児に大きな影響が生じることもあります。
AYA世代のがん患者が「できるだけ家で過ごしたい」と考えたとき、どのようなステップを踏めば在宅ケアを実現できるのか。かかるお金はどの程度で、使える制度はあるのか。具体的な手続きや進め方、AYA世代ならではの課題について、次回の記事で解説します。
(構成:ライター・松岡かすみ)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


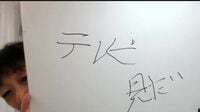




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら