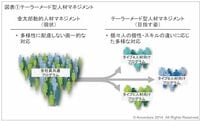「人事データ」を使い倒せば人事が変わる 「採用学」とは何を研究するものなのか

――「採用学」とはどのようなプロジェクトなのですか?

服部:企業と求職者の関係は、「募集のフェーズ」、互いに選ぶ「選抜のフェーズ」、そこから会社になじんで行き組織社会化する「定着のフェーズ」がありますが、そのプロセスを科学的に効率的にしようとしています。
ただし単に効率的だと、一方的な勝ちと負けが生まれやすい。どこで、なるべくwin-winに近いところを科学の観点から探る、ということがミッションとなっています。
採用の現場では、「面接でちゃんと評価ができているのか?」といった漠然とした問いは持っているが、じゃあ何が問題なのかがはっきりわからないことが多い。さらに、その検証のためには面接の評価を使えばいいのか、SPIのようなアセスメントのデータがいいのか、あるいは面接官が誰だったのかが使えるのか――、どれが使えるデータなのかがわからない。そこに私たちが入って、どんなことが悩みか、そしてそれを踏まえてどんなデータがあるのか?を確認して進めて行きます。
ただし、研究を進めるにはさらにもうひとつ乗り越える壁があって、それは「必要なデータを集めてくる」こと。社内にデータはあるが人事部の別の部署が……とか、営業実績のデータは自分たちの権限ではアクセスできない……とか。必要なデータをひとつのExcelファイルにそろえるまでに本当に時間がかかる。それが分析や検証が進んでいない大きな理由のひとつにもなっています。
そこはわれわれのような研究者の責任でもあるのですが、たとえば人事と経営企画と営業がデータを統合すれば実はこれだけのことがわかるのです、という世界を示して来れなかった。他方で、社内的にはデータがバラバラに取られてきたという経緯があって、それがミックスされてなかなかその問題に踏み込めなかったのではないかと思います。
――プロジェクトの「成果」はどのように定義しているのですか?
服部:採用の成果って難しいですよね。当たり前ですが究極的には「いい人材が採れてその人が中心人物として活躍をする」こと。ただこれだと採用以外にもさまざまな影響を受けてしまうので、採用学では採用の成果を2年ないし3年のパフォーマンスで定義しています。
これは適当に決めたわけではなくて、ある種の感覚と論理的な裏付けを踏まえて定義しています。日本企業であれば2~3年で仕事が1周して一人前として期待されることが多く、私たちのインタビューでも2~3年で現場で何か変化があるとよく言われる。また、3年で30%が離職するという議論もあります。であれば、マジックナンバーではないですが、おそらくそこには何かあるんだろうと考えています。