「人事データ」を使い倒せば人事が変わる 「採用学」とは何を研究するものなのか
――その中で、データはどのような役割を果たしているのですか?
服部:データそれ自体は、何も言い表していません。たとえば「血圧が120」ということ自体には意味がなく、「前回の100と比べて20も上がった」というように自分自身の現状や軌跡を知るために使うのが健全だと思います。われわれの役割のひとつは、直感的な判断をせず、数字が持つ怖さをなるべく排除して、議論の中でデータを読み解くために寄り添って行く、ということにある。
私たちが初めから「いい結果」「悪い結果」を提示すると、そこにロックインされてしまうので、代わりにグラフや数字が「なんでこうなるんでしょうか?」という質問をします。こちらの問いかけがフィードバックになっていて、それに対するフィードバックが実務家からもある。そういうリフレクションの繰り返しの場を作って行きます。「なんで80点だったのか?」「なんで相関していないのか?」ということに、当然、われわれも答えはわからないし、相手も答えを持っていない。
伊達:採用学プロジェクトのやれることは、問いを発掘して行くこと。解決するのが僕たちではなく、たとえば採用担当者の方と一緒に考えるべき問題だし、そこで答えが出ないのであれば、採用支援企業にも一緒に入ってもらう。そういうコミュニケーションのプラットフォームを作るのが採用学のスタンスですね。
服部:私自身はデータの分析はできるが、現場のことは知らないし、人事制度に落とし込むのにふさわしい直感を持っているわけでもない。一方で現場の人は、どんなデータがあるか知っていて、問いもモヤモヤと持っているが、それを解く術を知らない。だったら解決のアイデアを持つ相手を含めた3者が組めば、新しいものが生まれる可能性が高い。
その3者が議論するときに、われわれが抽象的な理論だけを押し付けてもダメだし、現場の言葉だけを並べられてもわからない。そのときに、直感的にわかりやすい数字というものが非常にいい思考材料になる。もちろん、わかりやすく高い低いとかが出てしまうところが、数字の恐ろしさでもありますが。
伊達:議論の交通整理をする感じですよね。現状として、本質的に採用をよくするためのコミュニケーションが発生しづらい。その交通整理というか、具体的にどういう課題があるのか、というのをみんながわかるような言語の形態やデータに落とし込んで、それを基に話し合えば、ある程度は今よりは建設的な議論ができてくると思います。
――今後に向けて、目指して行きたいことは。
服部:今の採用学では、まずはひとりの人が2~3年でパフォーマンスを出せるまでのミクロデータを説明しようとしています。少し先の話になるが、この先にさらに企業の業績が上がるというのがあればよい。今は個人個人のパフォーマンスの集積があれば企業の業績もよくなる、という論立てでやっている。
伊達:自分たちのビジョンとしては、採用の効率化をもっと普及させたいが、考え方の普及、啓蒙とかはどうしても限界がある。たとえば今日のような話を、使いやすい、使いたい、と思えるようなツールに落とし込む、ということがひとつの方向性としては考えられます。
もう一点は、底上げとして、データに対する姿勢や考え方を育むような講座やトレーニングは、同時並行でやっていきたい。シンボリックな成果を作る、パッケージに落とし込む、講座やトレーニング、この三位一体で進めて行くことになると思います。
服部:マーケティングの分野では昔から言われていることですが、採用においてもアーリーアダプターはごく一部しかない。それが地方の企業など、超ビッグ企業じゃないことも多い。そういうところから生まれてくるイノベーションを、われわれとしても大切にしていきたい。ただ、そこだけをやっていても世の中はよくならないので、トップランナーと1対1をやりながら、同時に普及・底上げも進めて行きたいですね。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



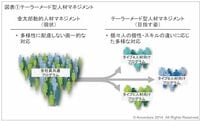





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら