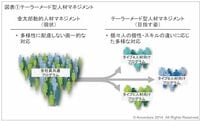「人事データ」を使い倒せば人事が変わる 「採用学」とは何を研究するものなのか
――具体的に取り組んでいることは?
服部:一例を挙げると、2~3年後のパフォーマンスにつながる採用基準って何だ?ということを調べています。言い換えれば、企業としては2~3年後の成果につながる指標を探そうとしているわけです。
候補者がエントリーをして、採用面接が3回、4回と進んで行く中では、それぞれのフェーズの面接評価があり、適性検査などのテストデータもあります。他方で、会社に入社して2~3年目くらいの360度評価や業績などのパフォーマンスのデータもある。たとえばこれを分析すると、適性検査のAという項目は成果につながるけど、Bというものはつながっていないかもしれない。あるいは、面接を3~4回やっているが、1回目の面接で評価が高かった人は、2回目でも3回目でも高い。だとすれば、そんなに回数やらなくてもいいんじゃない?という可能性が出てくる。さらに興味深いことに、その高く相関した面接の評価と、入社してからのパフォーマンスが必ずしも相関していないこともある。それは何を意味しているのだろうかと。

伊達:企業としては、採用においてもPDCAのサイクルを回したい。あるいは、回さなければならない。しかし、現状では振り返るための技術や方法論が十分にあるわけではなく、不安なままで進めている。不安だと、人間は「いろいろやる」んですよね。適性検査も面接もやって、さらに能力試験もストレス耐性も見よう、と。
しかし、どれがよかったのか悪かったのか、それを判断するロジックや定量的な基準がない。そうなると「来年どうしよう?」と考えるときに、わからないけど新しい取り組みをほとんど直感に基づいて追加してみることになる。採用学がやっていることの実務的な文脈としては、特定の成果変数に対しての影響度合いを棚卸しして、選択と集中ができるようにする、という意味合いが大きいと思っています。
服部:企業においては、儲けるという論理とムダを省くという論理がありますが、人事では後者の論理がまずはわかりやすいですよね。今、おおよそわかっているのは、面接は平均で2~4回くらい、15~40分くらいやっている。これを応募者の人数と単純にかけ算すると、大切なスタッフがこれだけの時間を使っています、とわかりやすく数字で提示できる。これを2分の1とか4分の1にできますというのは、インパクトありますよね。
もちろん、面接は面接である種の基準をすごく高い精度で測っているのかもしれない。しかし、それが本当に採用プロセスの中で測りたいものなのか?という話を、ぼくらが言うというより、データを見せると現場が気づくんですよね。「なんでここは相関していないんだろう」「俺らは何をしていたんだろう」と。そういう瞬間がすごく大事で、データそのものが相関していないということよりも、その後にくる「私たちのやってることは……?」というロジックを考えることが大切。