老夫婦が辛苦を乗り越えて福島に帰った理由 故郷へ戻ることに理屈なんてない
その言葉を聞いたとき、私の中にすとんと落ちるものがあった。木幡夫妻は帰りたいんじゃない。帰らなくちゃいけないから、故郷に帰るんだ。世間が抱くような、避難者が故郷を恋しがる感動のストーリーは、尭男さんの口からは語られなかった。彼はただ、縛られていて、故郷が自分を離さない。だから故郷に帰らなきゃいけないんだ。家や墓、土地などのしがらみが複雑に絡み合って、彼らを動けなくしている。この気付きが私の疑問を軽くしてくれたと同時に、尭男さんの言う「故郷」は誰もが心のどこかに持っているものなのだろうかと考えた。
「おカネで計算できないよ。今でもじっとしていると、あのときあんな話をあの土手でしたな、あそこの芽吹きがきれいだったな、と思い出す。山であり川であり、田畑であり人であり。故郷とは、生きる上での『ごはん』のようなものなんだよね」
衣食住と同じように、彼らにとって故郷とは、生きるために必要な要素の1つなのだ。木幡夫妻は、私に「故郷」という言葉の本当の意味を教えてくれた気がする。私を縛る、不動の場所。私に故郷はあるだろうか。
「当たり前」の向こうにいる人を考える
2018年3月に、彼らは福島に帰った。残りの人生を南相馬で過ごす。決して安全が保障されているわけではない。それでも夫妻はこの道を選んだ。それは5年間の避難生活を経て決心した選択ではなく、2011年3月11日、家を飛び出したあの日あの瞬間から決まっていた選択だったのかもしれない。
東京などの離れた地域で被災地・福島を考えることは非常に難しいと感じる。特に、1分1秒で情勢が変わる首都圏は、情報は過多、刺激的な出来事に溢れている。きっと東京には、被災地を考えるよりも「大事なこと」が沢山あるのだろう。それでもこれだけは忘れないでほしい。
煌びやかなイルミネーション、帰り道に照らしてくれる電灯、スマートフォンの充電を助けるバッテリー。そのコンセントの先にあるのが、福島だということを。私たちの生活を豊かにしてくれていたエネルギーは、福島の人々の生活と安全と引き換えに存在していたということを。
「復旧も復興も先が見えない福島に、私たちは何ができるの?」
できることは、沢山はないかもしれない。でも、少し。少しでいいから想像してみよう。この電気はどこからやってくるのだろう。誰がスイッチを押してくれているのだろう。これは福島と首都圏の関係だけではない。毎日のお弁当は誰が作ってくれるのか考えてみよう。毎日のごみは誰が収集してくれているのか考えてみよう。
木幡夫妻が失った故郷。そして再び帰る、故郷。彼らの選択は私に、地域と人とのつながりを考えるきっかけをくれた。
想像力は感謝につながる。感謝は人を豊かにする。当たり前に疑問符を持つこと。この小さな心がけの連鎖が、私たちができるもっとも息の長い支援なのではないだろうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

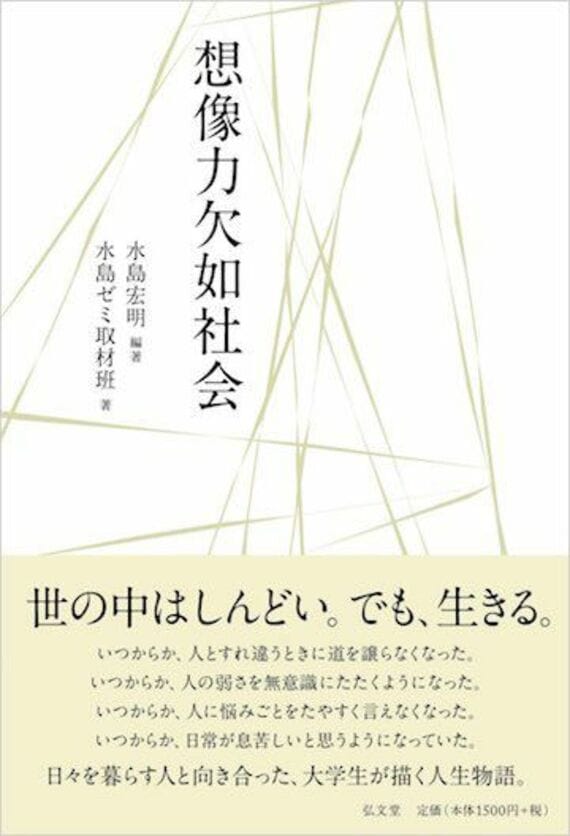






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら