
01. 「宮大工」とは神社仏閣など日本古来の木造建築を手掛ける大工のことで「堂宮大工」「宮番匠」とも呼ばれる
02. 宮大工の起源は約2500年前の中国にさかのぼるといわれ、日本へは朝鮮半島を経由して伝わった
03. 日本の宮大工の歴史は飛鳥時代に朝鮮から来た僧侶・慧滋と慧聡が「飛鳥寺」を建造したことにはじまる
04. 飛鳥寺は6世紀末に百済から仏舎利が献じられたことにより蘇我馬子が建立を発願し建立された
05. 慧滋と慧聡に教えを受けた聖徳太子は「法隆寺」を造り、その後さまざまな歴史的建造物を建立した
06. かつては専門の大工ではなく、僧侶自身が寺社の建築や修理に携わるケースも多かった
07. また宮大工は一カ所に留まらず各地の神社仏閣等を渡り歩いて仕事をするため「渡り大工」とも呼ばれた
08. 宮大工の特長的な技術がくぎや金属のボルト等を使用せずに木材だけで建物を組み上げる「木組み」である
09. これは木材同士をパズルのようにはめ込む加工をすることで固定し、高層の建物から重力を分散させる
10. 宮大工は、温度や湿度による木の変形や、かかる力の強さや方向の変化などに合わせて加工法や木を変える
熟練の宮大工による手刻みならではの手法の数々
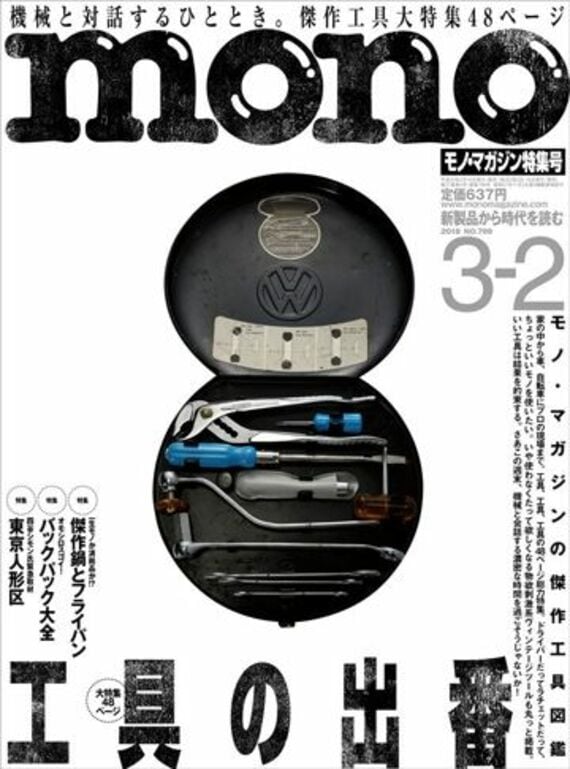
11. そのひとつ、「継手」というのは、材木の長さを増やすために木を継ぎ足すときに使用される手法である
12. なかでも「腰掛鎌継ぎ」は主に土台や桁で使用され、下の木を上木で押さえつけるように組む
13. 「追掛け大栓継ぎ」は上木を横からスライドさせてはめ込む手法で、腰掛鎌継ぎより複雑な分、強度も高い
14. 「腰入れ目違い継ぎ」は上木に木のねじれを防止する〈ねじれ止め〉が施されているのが特長
15. これはとても複雑な形状の継手で、熟練の宮大工による手刻みならではの手法といわれている
16. 「大栓継ぎ」とは梁を太い硬木で固定して納める手法で、非常に高い大工技術が要求される
17. ふたつ以上の木材をある角度に接合する手法を「仕口」といい、土台と柱、梁と桁のつなぎ目などに使われる
18. 小屋梁でよく使用される「兜蟻掛け」や「大入れ蟻掛け」など、仕口にもさまざまな手法が存在する
19. 継手や仕口、その他の接合部分など部材の形状全般を曲尺1本で作り出す手法を「規矩(きく)術」という
20. 「規で円を正し、矩で直角を正す」といわれ、宮大工になるためには必ず身につけなければならない


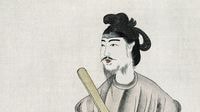





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら