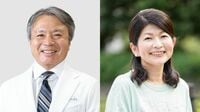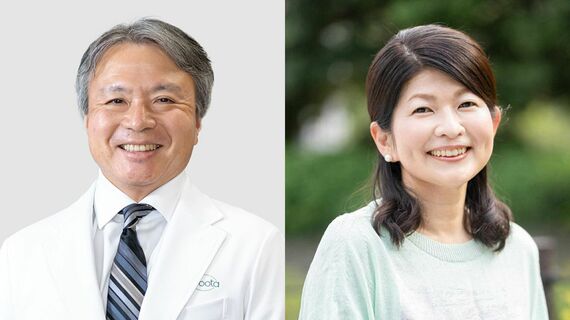
多様な選択肢があっても、家庭によってハードルが
窪田:学校に行かない子どもには、具体的にどんな選択肢があるのでしょうか。
白井:今は昔に比べて多様な学びの場所が作られているので、オルタナティブスクールやフリースクールを選ぶこともできます。とくに小学校では、ほとんどの教科を一人の先生が教えますよね。この先生との相性が悪いことも、子どもの不登校につながる可能性があります。一方でインターネットの世界では、いろいろな配信者のチャンネルの中から、子どもが自分に合った先生を見つけることもできます。
窪田:日本の教育は「選べない」ことが問題だとお話しいただきましたが、選ぶためにも知識や条件が必要なのでは?
白井:重要なご指摘です。多様な選択肢があっても、それを活用するにはまず知ることが必要ですね。つまり、情報にアクセスできるかどうかという一つ目のハードルがあります。