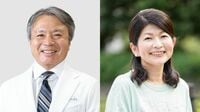白井:発達の凸凹や個人差など、近年になってわかってきたことも多くあります。また、英語が小学校から必修化されたり、プログラミングなど新たな学習内容が追加されたりもしています。変化の激しい社会に対応するため、先生方は自分たちも教わっていないことを子どもに教えなければならなくなりました。指導する側に求められるスキルは昔より上がっているので、教員養成の段階から、大きな改革が求められていると思います。
窪田:対象の子どもの年齢が低いほど、一人の先生が大人数を見ることは難しいでしょうね。中国が学校を変えようとしたとき、まっさきに取り組んだのは教員の再教育だったと聞きます。子ども一人ひとりやその保護者を直接変えようとするよりも効率がいいと思うのですが、日本でそうした合理的な議論ができないのはなぜでしょうか。
「変えたくない」という人が多すぎる
白井:「変えたくない」という考えを持つ人が多いのだと思います。例えば、政治家などを見ていても感じませんか? 自分が育った時代の古い価値観を持ち続けていて、自分が体験してきたことが正しいと信じている大物議員っていますよね。自分が成功したのもそのおかげだと思っているので、「過去の強制的な教育がよかった」「今はそれがなくなって甘くなったから、子どもが学校に行かなくなっている」などと声高に言う。しかも彼らは成功者だと自他ともに認識されているので、その影響力も大きくなる。
窪田:なるほど。変化しにくい社会には、日本の国民性も関係していると思いますか?
白井:国民性かはわかりませんが、この感覚は、偉い人だけでなく一般市民にも意外なほど深く根差しているとは思います。自分が体験してきたものを「正しくなかった」と批判するのは、心情的にもなかなか難しいことです。その点を理解しながら社会にアプローチする必要があると考えています。