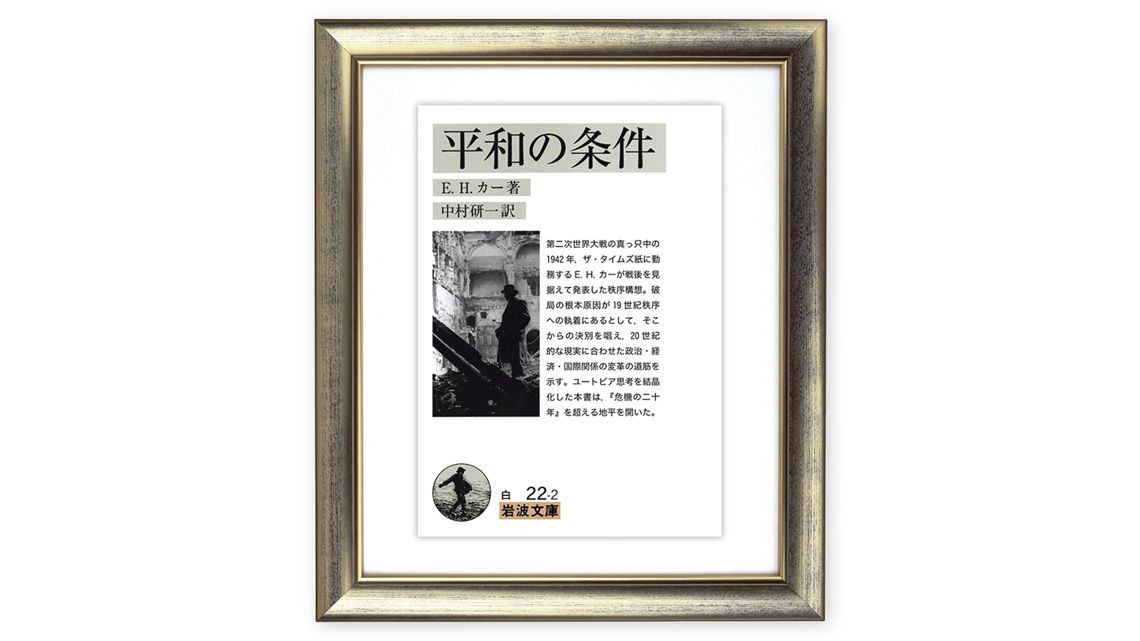
なぜ19世紀の世界は壊れたのか。カーはその背後に、自由民主主義・民族自決原則・レッセフェール経済の是非をめぐる大国間の対立をみた。カーの考察の要旨は次の3点だ。
カーの考察の要旨
第1に、最大多数者が自らの利益のために政府機関を統制する民主主義は、20世紀に入り普通選挙が行われるようになったことで、大衆を基盤としつつも実際には経済権力主導となった。これは、国家に対する共通の義務感や道徳を喪失させた。
第2に、民族自決が重視された結果、国々は細分化され、各地で紛争が起こった。だが民族の定義はあいまいで、西欧以外において民族=国家の図式がすんなり成立するわけでもない。また、国際社会では強国の主張が通りやすい。とくに戦争時には、小国同士が集まる集団安全保障は維持困難で、小国は強国に従属して生存を図らざるをえない。だから、軍事的・経済的目的のためには国家よりも大きな単位が必要で、民族自決の権利は、軍事的・経済的義務の相互分担の枠内で初めて有効になる。

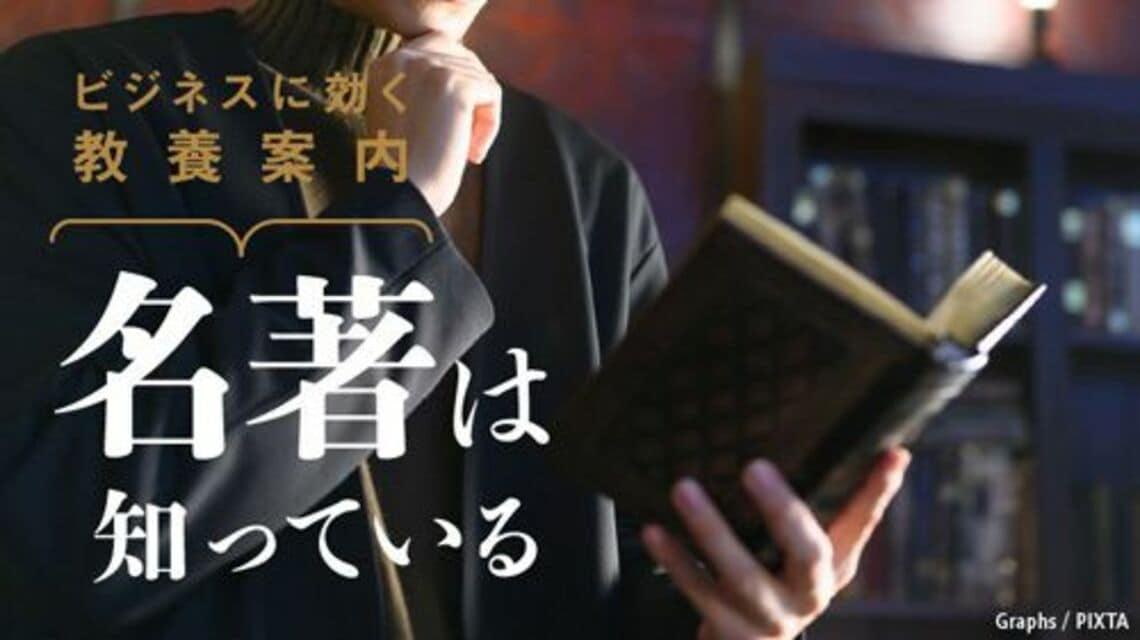
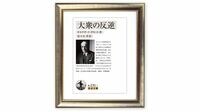






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら