
令和のコメ騒動がいつ始まったのかという点には諸説あるが、スーパーの棚からコメが消えるという衝撃の事態からは1年以上が経過した。それ以降、コメの価格は約2倍に高騰し、コメに関するニュースを新聞やテレビで見なかった日は、ほぼなかったと言っていい。
筆者も一応専門家として、「いつコメの価格は下がりますか」と聞かれ続け、「そろそろ下がるのでは……」と答え続けて1年が過ぎた。
あふれるニュースの中には、真偽不明の情報も多かった。それらの情報がコメ市場の先行きの不透明さを強め、さらにニュースが過熱するという悪循環もあったように思う。
そこで本稿では、筆者の目にとまった「過大評価」とでもいうべき言説を3つ挙げ、そのようなニュースに対する向き合い方について考えてみたい。
時を同じくして始まった「先物取引」
1つ目は、先物市場の開設が米価高騰の要因となったという説である。
堂島取引所で「堂島コメ平均」という先物商品の取引が始まったのは2024年8月であり、確かに時期としては米価高騰が始まった時期と一致する。
しかしながら、堂島コメ平均は政府が公表している相対取引価格を基準とした指数を取引するものであり、現物の取引は行われていない。よって、先物取引が始まったからコメ不足になったわけではない。
また、先物市場の取引自体は低調という評価が一般的である。
例えば、日本経済新聞(25年8月13日付朝刊)と日本農業新聞(25年8月14日付)はともに、開設1年を経て先物市場の利用は低調と報じている。市場創設時には透明性の高いコメの価格形成に貢献することが期待されていたが、まだそこまでの影響力はないと言わざるを得ない。
それにもかかわらず先物市場が米価高騰の犯人として取り沙汰されたのは、「先物=投機」というイメージが根強く残っているからであろう。

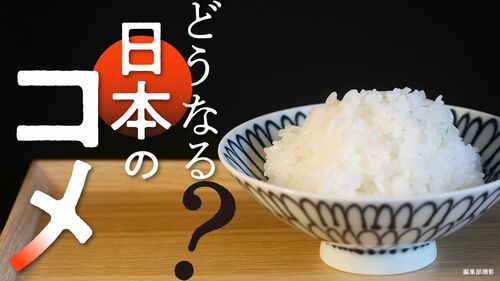































無料会員登録はこちら
ログインはこちら