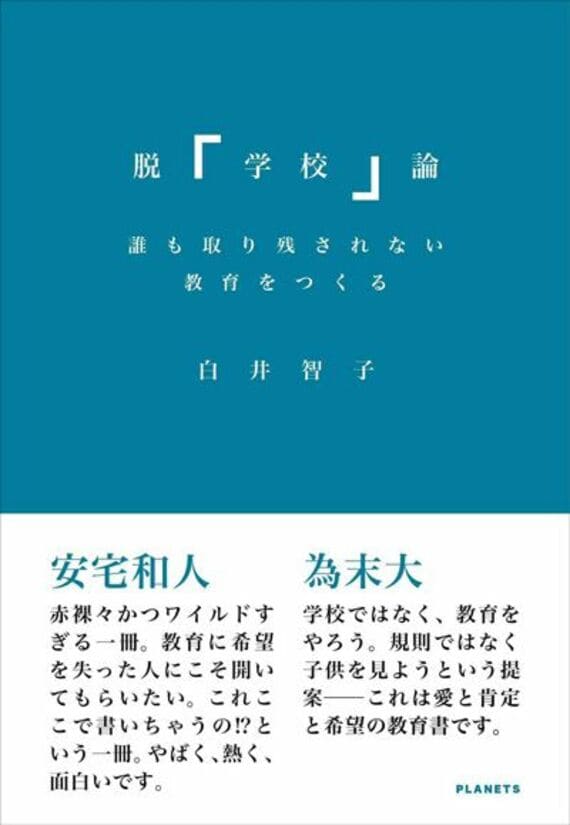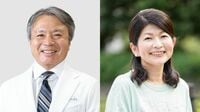白井:もう一つ、経済面のハードルがあります。往々にして、フリースクールなどでは公立の学校よりもたくさんのお金がかかります。これらのハードルが越えられない、あるいは選択肢があるという情報へのアクセスがない家庭だと、子どもは家にいるしかなくなってしまいます。不登校のわが子に対して「学校に行っていないんだから家から出るな」と言う親もいます。これでは引きこもりまっしぐら。学校に行けていないならなおさら、会える友達には会ったり、習いごとには行ったり、外とのつながりが切れないようにすべきです。
また、地方に行くほど、学校以外の通える場所がなくなるという問題もあります。そうした場合は塾でもいいし、地元のスポーツチームでもいい。とにかく、学校と家庭以外の居場所を増やしていくことが大切なのです。周囲の大人にもこうした意識を持ってほしくて、昨年末に『脱「学校」論』本を出しました。「学校に行けないことが問題ではない」だということを、もっとたくさんの人に知ってほしいと考えています。
日本の学校教育は「伝統芸能」的?
窪田:不登校への対応や学びのあり方については、国の対応も変わってきてはいるのですよね。
白井:今は不登校を理由とした転校や、家庭での学習も認められるようなりました。また、2021年ごろから「個別最適な学び」の必要性が注目されるようにもなっています。AIやデジタル技術を活用した教材のほうが適している学びもありますから、必ずしも無理やり子どもを教室に集めなくてもいいという発想が生まれています。
もちろん、集団のコミュニティーでしか身に付けられないこともあります。ただ、日本の学校は社会の変化に比してあまりにも旧態依然で、伝統芸能のように同じことを伝え続けてきたと感じています。