アルビノの動物は、虹彩や網膜、脈絡膜にメラニン色素がないために、眼球の中で光がハレーションを起こしやすい状態になっています。写真を撮るときも、太陽光や照明の光がレンズに入り込むことで、ハレーションを起こしますよね。
アルビノの動物は、その珍しさからペットとして人気の種類もいますが、基本的に光に弱い動物なので注意してあげてくださいね。
瞳孔の形が違うわけ
虹彩の真ん中には丸い穴が開いていて、ここが瞳孔です。虹彩には瞳孔を開いたり閉じたりする2種類の筋肉(瞳孔括約筋と瞳孔散大筋)があって、光量が強いときは、瞳孔の大きさを小さくして目に入る光の量を少なくし、反対に、光量が少ないときは瞳孔を大きく開いて光を多く取り入れようとします。
人やイヌは丸い瞳孔をしていますが、ネコやキツネといった夜行性(実際には明け方と夕暮れが活動時間)の動物は、瞳孔が小さくなるときには縦に細長いスリット状の形になります。
縦長の瞳孔のメリットは、瞬時に瞳孔を大きくしたり小さくしたりすることができるところにあります。
ネコを飼っている方は、暗い部屋では大きく丸い瞳孔が、電気をつけたら瞬時に細長い瞳孔に変わるのをよく目にしますよね。ネコやキツネは茂みなどに隠れて獲物を狙う待ち伏せ型の捕食者であり、瞬時に瞳孔の大きさを変化させることで、的確に獲物に狙いを定めることができるのです。
一方、ウシやヤギ、ウマなどは横長の瞳孔をしています。これらはいずれも常に外敵に狙われやすい草食動物であり、横長の瞳孔の方が広い視野を確保するのに有利なのでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

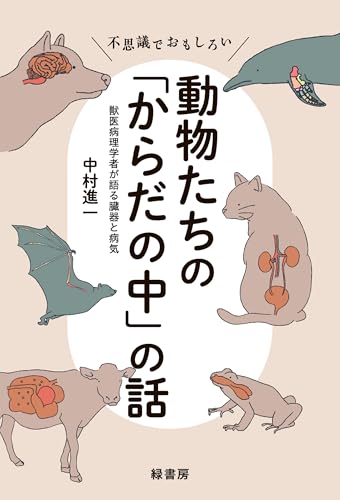































無料会員登録はこちら
ログインはこちら