中国で《抗日映画》が“興収500億円超え”のヒット。鑑賞後に「子どもが日本アニメのカードを破り捨てた」との報道も…。戦争と教育を考える
いつか、日本と中国の国旗が共に舞う共同の戦争博物館ができたらと祈願せずにいられない。場所は南京。現在の南京は「博愛の都」とも呼ばれ、文学や芸術が盛んな都市だ。
将来、日中共同戦争博物館は記憶の共有と対話の場になり、両国がそれぞれの視点から戦争の記憶を展示し、過去の苦しみや犠牲を認め合うことで、歴史の一方的な語りを超えた「共感の空間」が生まれる。
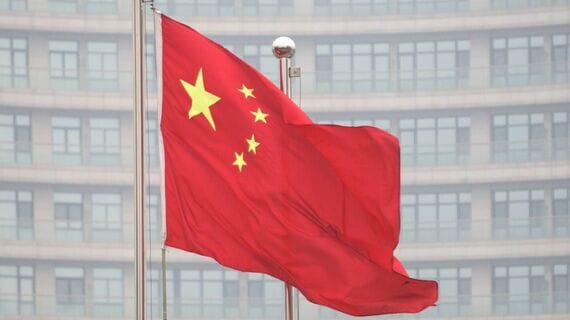
子どもに“未来への希望”を感じさせたい
実は、日本と中国には、すでに地域的な民間戦争博物館が多数存在している。これらの施設は、戦争の記憶を伝えるために設立され、地域の歴史や個人の証言を中心に展示を行っているものも多い。
民間の戦争関連の博物館は、中国ではまだ数は限られているが、政府主導の論調とは異なる視点を提示する民間の記憶空間だ。例えば、四川省成都市大邑県安仁鎮にある「建川博物館」(2005年開館)は、民間人によって設立された大規模かつ多様な博物館群であり、戦争の記憶を中心に、災害、民俗、文化など幅広いテーマを扱っている。
日中の民間博物館が、民間の交流を育む場となれば、どれほど希望に満ちた未来が開けるだろう。たとえば、博物館を拠点に、両国の若者が共同で歴史を学ぶプロジェクトを立ち上げる。さらに、収蔵資料をもとに、戦争と和解をテーマにした芸術作品――映画や演劇などを日中共同で制作することも夢ではない。
両国の視点から戦争を描く芸術作品は、加害・被害、兵士・民間人、勝者・敗者という二項対立を超えた「人間の物語」が生まれるはずだ。「エンタメ+平和メッセージ」の新しい日中合作モデルになり得る。これらの作品は、子どもたちを悲しませるのではなく、未来への希望を感じさせるものとなるだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら