M型ワークフローのうち、「報連相」と呼ばれているものに該当する範囲は赤線で示したVの部分だろう。それに「①仮説立て」「⑤自己アップデート」を加えたのは、筆者の体験がもとになっている。
前職時代、上司から常々言われた「目的のない報連相はするな」「1の情報を伝えるのに10の時間を使うな」というしつけのおかげで、筆者はコミュニケーションの時間対効果(タイパ)の重要性を叩き込まれた。その結果、試行錯誤を繰り返して形となったのがこのワークフローなのだ。
まずは自ら仮説を立てることで業務に取り組む上で不足している認識や情報が炙り出せるし、事前確認する際も自分が立てた仮説が合っていれば上司の確認対応は「この仮説でOK」と回答するだけなので時間が削減できる。これが最高効率の事前確認。そして、ひとつの業務実行から「同じミスをしない」「より対応力を上げる」という自己成長までを一連のサイクルと認識し、繰り返していくことで、「自走できる人材」に育っていくことができる。
報連相を提唱すると「コミュニケーションを取ること自体」が目的と誤認されやすいが、このM型ワークフローであれば「業務実行」のために何を準備・確認すべきか、何を上司とすり合わせておくべきか、一目瞭然になる。外資系企業の多くがそうであるように、部下に一定の決裁権を与える場合でも、このワークフローだと混乱は生じないだろう。
曖昧な概念を一度クリアに
限られた人材で、最大限の成果を出すことは、すべての企業にとって共通した目標だろう。ここは一旦、あまり機能していない「報連相」という曖昧な概念を一度クリアにして、M型ワークフローを試してみてはどうだろうか。
筆者自身がそうであるように、多くの部下、上司にとって「やることが明確になって、最小限のコミュニケーション工数で、実行すべき業務に割く時間が増える」ことにつながると思う。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら













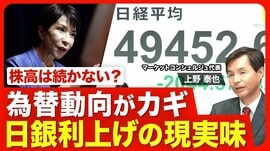


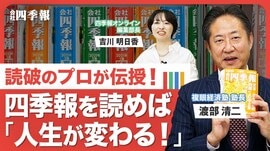




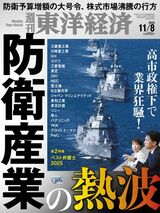









無料会員登録はこちら
ログインはこちら