実際、外国人労働者からも「報連相と言われても、何をどこまで上司に伝えるべきか分からない」「定義が曖昧すぎる」という声が聞かれるが、その意見は日本人の筆者が聞いてもまっとうだと感じる。
本稿では、今まで日本中が”なんとなく”使ってきた報連相について、問題点を整理したうえで、より成果につながる仕事の進め方である「M型ワークフロー」を提唱したい。
報連相の最大の問題点は「定義」がハッキリしないこと
報連相の最大の問題点は、定義がハッキリしないことだ。Geminiに「報連相の定義は?報告・連絡・相談は、具体的に何が違うの?」と聞いてみると、以下の回答を得られた。
| 報告 | 上司や依頼者など、指示を出した人に対して、仕事の進捗状況や結果、あるいは発生した事柄について事実を伝えることです。 |
| 連絡 | 業務に関わる事実や決定事項を、関係する全ての人に広く、簡潔に伝えることです。 |
| 相談 | 業務上の問題や疑問、判断に迷うことが起きた際に、上司や先輩、同僚などから意見や助言を求めることです。 |
何か違いがあるように見えるが、「そこまで違うか?」「わざわざ分けるほどのことか?」と疑問が湧いてくる。
少し調べてみると、報連相の研修は今も昔も数多く行われており、「報連相はもう古いから『確連報(かくれんぼう)』をやるべきだ」とか「上司に必要な態度は『おひたし(怒らない、否定しない、助ける、指示する)』だ」など、言葉遊びのようなビジネスマナーを多く見かける。ビジネスマナー大喜利のような状況だ。
筆者は新人時代、「報連相とは、報告と連絡と相談のことです」「上司には報告、広く情報共有する連絡、悩みがあれば相談」と教えられた。日本語の意味として似たような3つの単語を使っているので、「?」となってしまった。結局「とにかく迷ったら上司に情報共有しておくか」くらいしか理解できなかった。













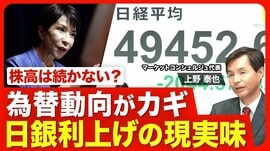


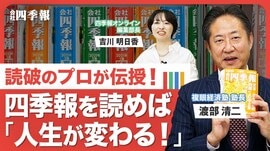




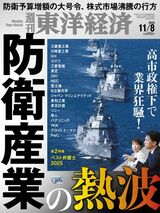









無料会員登録はこちら
ログインはこちら