【M型ワークフロー】
<例>
マネージャーから依頼された業務において、以下のような項目を整理する。
・何のためにやるのか?(目的)
・どのようにやるのか?(やり方、進め方)
・どうなれば完了、成功なのか?(ゴール設定)
・他の依頼業務と比較して、どの程度の優先度なのか?(優先度、実施する順番)
・いつまでに完了すればいいのか?(納期)
・過去に実施した類似の業務や事例がないか?(類似事例の確認)
・この業務を行う上で依存関係にある業務、人、情報、スキルは何なのか?(依存関係の確認)
<例>
・実行した結果はどうだったのか?
・うまくいかなかったこと、残っている問題点はないか?
・追加で実施すべきことはないか?
・追加実施すべき業務はどのように進めていこうと思っているのか?(②を部分的に繰り返すイメージ)
<例>
今回の業務実行を振り返り、
・改善すべきことはなかったか?
・不足している知識、スキルはなかったか?
・改善すべきこと、不足している知識やスキルがあるのであれば、具体的にどう改善するのか?(改善計画を上司に相談してみると尚良し)
※実際の業務においては、このサイクルを何度も繰り返しながら業務完了を目指していくことが一般的
このM型ワークフローを各チームや各人ごとに作成することで、実行の前後で何を確認、報告すべきか具体的にルールとして徹底できる。目的が曖昧な「何となくの報連相」に余計な時間を費やす必要がなくなるのが最大の利点だ。













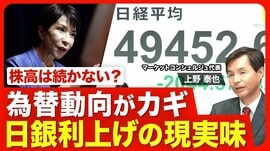


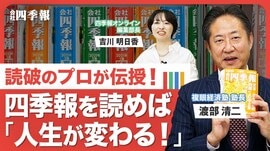




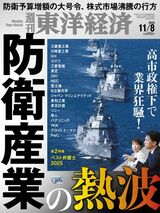









無料会員登録はこちら
ログインはこちら