リクルートマネジメントソリューションズが行った「上司からの管理過剰感に関する調査」では、報連相についても「忙しくてもわざわざ文章での報告を求められる」「現場のことを事細かに聞いてくる」「今どこで何をしているのか、行動をいちいち共有させられる」など多くの不満が見られた。
こうした膨大な量のコミュニケーション義務によって部下も上司も疲弊してしまうのは、そもそも報連相の「目的」が不明確なことが原因だと思っている。
上司がすべきことは「ルール」を決めておくこと
もちろん、上司と部下の間でコミュニケーションを取ることは重要だ。特に新人の場合、事前の確認をせずに業務を実行してしまうと、「いや、全然意図と違うから……」となってしまうことは少なくない。業務を実行する前に、上司との間で目的や実施方法、納期などをすり合わせてから取り組むことで、上司が想定した形で依頼業務が進む。
では、上司と部下の間でどのようなことを取り決めてコミュニケーションを取れば、「報連相でやりたかったことが実現する」のか。一言でいえば、「仕事の目的と実行のズレをなくすコミュニケーション」が必要だ。
当然だが、主体は仕事の「実行」である。その実行が目的からズレてしまうと、いくら時間をかけて努力しても、成果も評価もゼロになる。だから、実行の前と後に、目的や進め方を都度確認した方がいいのだ。
上司から依頼されたり、自分の役割として担っている業務において、その業務を実行するために必要な情報を上司と共通認識を持った上で進めるため。
・業務を実行する前に認識をすり合わせるための事前確認を取ってほしい
・その際に確認する項目は「業務の目的」や「進め方」など ※これは上司によって事前に確認したいことが異なる
・業務を実行した後には「どうなったのか?(結果)」を必ず報告してほしい
・業務を実行している際に「問題が発生した場合」「状況が変わって対応方針に迷いが生じた場合」は、その時点で状況を共有してほしい
このようなルールを事前に取り決めておけば、不必要なコミュニケーションを取る必要がなくなるし、定義(正解)が明らかになっているので、それに沿って教育することができる。













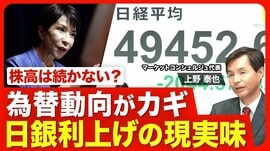


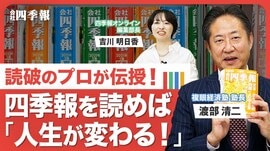




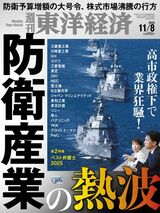









無料会員登録はこちら
ログインはこちら