「店員が元気よく歌う」→「待ってるこっちは恥ずかしい…」 一世を風靡するも、残り1店となった「コールド・ストーン」。衰退も"納得"の理由
「体験価値」と言うけれど
近年、チェーンをはじめとする外食では「体験価値」ということがしきりに言われている。デリバリーやテイクアウトが普及するとともにインフレが進んで中食需要が上がる現在、わざわざ行く外食に求めるのは「ワクワク感」をはじめとする体験価値だというのだ。
例えば、厨房の風景が見えるようになっていたり、トッピングを店員さんが目の前で盛り付けてくれたり……と、さまざまな形で「体験価値」が押し出されている。
すかいらーくグループが出店した「イタリアン リゾート ペルティカ」は、客が刻んだバジルを料理にしてくれるという。その間に、店員さんとの間にコミュニケーションが生まれ、楽しい外食体験を……となるわけだ。
ただ、コールド・ストーンの例を見ていると、やはり単に「体験させればいい」というものでもない、と思う。
むしろ、チェーン店の場合、「体験価値なんて求めてないよ、むしろ人とそこまで関わらないのが気楽なんで……」と思っている人もいるのではないだろうか。
作家でエッセイストであるpha氏はこう書く。
今の文脈でいえば「むきだしのままで直接コミュニケーション」をするのが、「体験型」の飲食が目指しているものだ。
マニュアルがあるにしても、まるでそれがないかのように「生」の会話の楽しみを与える。しかし、それはめんどくさい。pha氏のように思っている人は意外と多いのではないか。
けれど、このことは、どんな飲食チェーンの研究や公式ホームページを見ても書いていない(エッセイのような個人的な文章には書いてあるかもしれない)。
なぜなら本来「人と関わらない」はマイナスなことで、堂々と言えるようなことではないからだ。「人とのあたたかなふれあいを当店で」などの言葉を並べたほうが聞こえはいい。

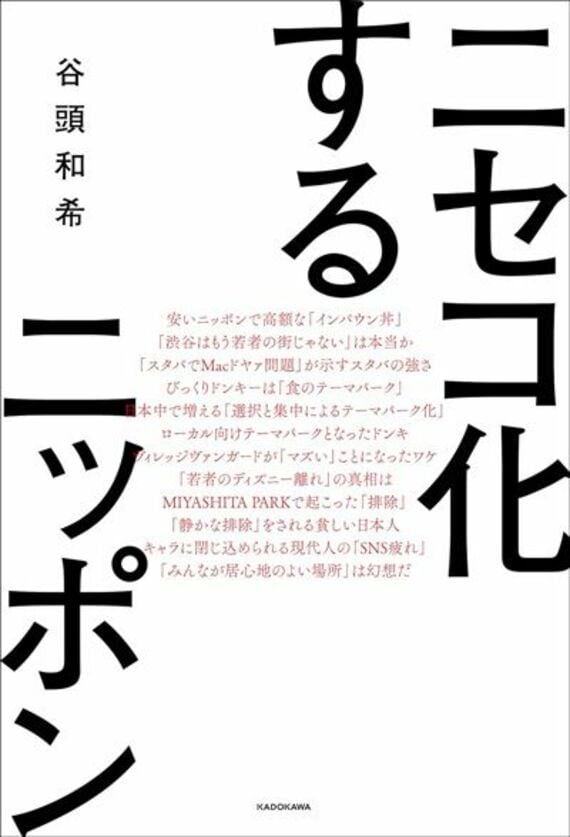
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら