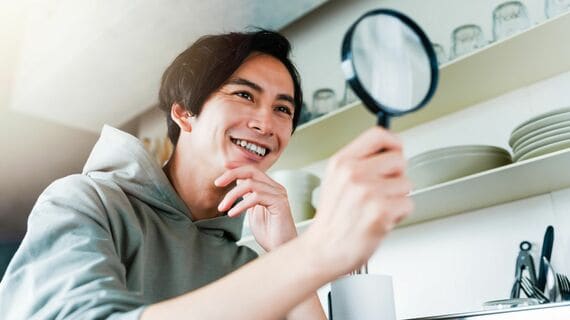
好奇心がすべての入り口
好奇心とは、「自分の知らないことや新しいこと、珍しいことなどに興味を持ち、ものごとを探求しようとする根源的な心。自発的な調査・学習やものごとの本質を研究するといった知的活動の根源となる感情」をいいます。
先が読めない時代、ピンポイントで目標が設定できないような時代だからこそ、できるだけ多くの情報を貪欲に取り入れ、そこから何かを見つけ、気づき、深掘りし、新しいビジネスの種を見つけだすことが求められています。
そして、それを楽しめることが大切です。
その入り口となるのが好奇心です。すべての入り口が好奇心です。目の前のこと以外に興味がない、好奇心を持てないのは致命傷です。
今まで一緒に働いて、楽しかった人、尊敬できた人を思い出してください。好奇心旺盛な方ではなかったでしょうか。何でもよく知っているなという人は、必ず好奇心旺盛な人です。
周りを見回して、活き活きしている、一緒に居て楽しい、面白いと思う人の多くは、何にでも興味を持って取り組む、雑学が豊富な人ではないでしょうか? そんな人と働いたほうが楽しいし、自分も知識がつくと思いませんか?
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら