韓国語の「辛い」は約20種!言葉の解像度の地域差 フィンランドの「雪」は約40種、日本語に多いのは?
北欧のフィンランドでは「雪」を表す言葉が非常に多く、駐日フィンランド大使館のX(旧ツイッター)の公式アカウントによると、雪の固さや湿り気などの状態によって40以上もの言葉を使い分けているそうです。
日本で出世魚と呼ばれる魚は、同じブリでも成長段階によって呼び名を4つくらいに分けて表現します。しかし英語ではブリはもちろん、ヒラマサやカンパチなどもひっくるめて「イエローテイル」の1語で括られるのが通常のようです。
「山紫水明」は言語化力の極み
「山紫水明」とは自然の景観を表現した日本の言葉ですが、ここでいう「紫」とは、山々が日の光の中で紫色のごとく目に映る様を表しており、湿潤地である日本ならではの表現と思われます。乾燥した南米の高地やアフリカの砂漠地域などでは、なかなか生まれることがなさそうな言語表現です。
ちなみに、この語は江戸時代の文人、頼山陽が京都の鴨川近くの書斎から見た東山と鴨川の様子を表現したものです。個人の体験が普遍的な言葉になることもあります。これぞ言語化力の極みです。
その土地ならではの言葉が必然として生まれ、そこで暮らす人々の心情が彩られていく。コミュニティの差異の中でそれぞれの言語が固有の発展を続け、風土に応じた意味を持ちながら言語表現がなされてきたのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

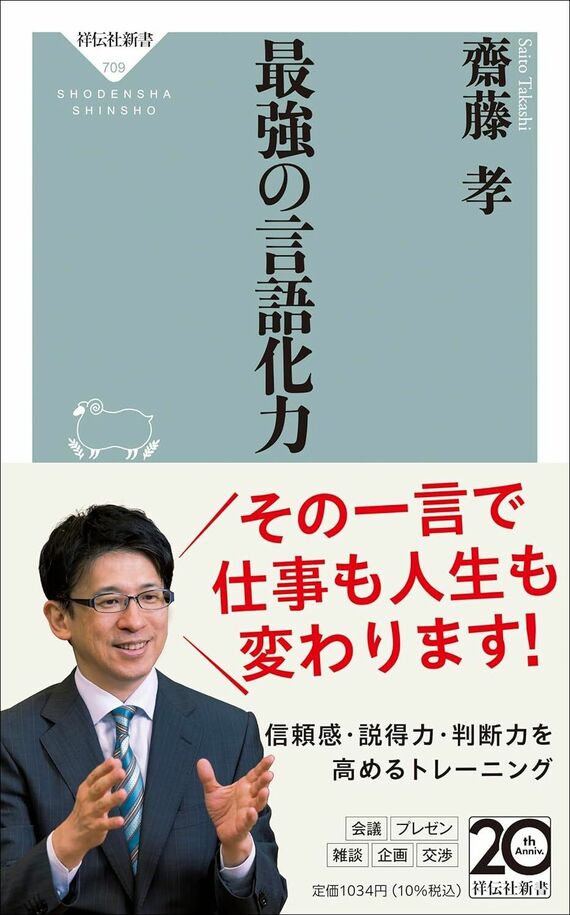






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら