要注意「年金の確定申告をする人」に教えたい盲点 2024年分の「定額減税」はどう処理すべきなのか
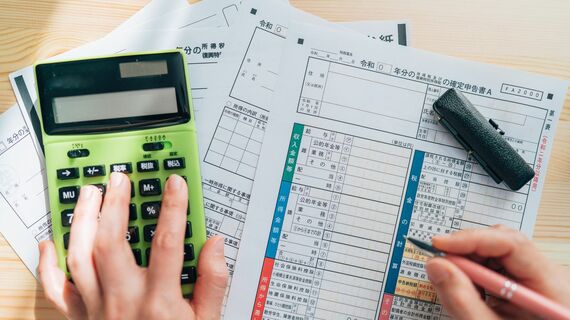
公的年金の受給者は原則、確定申告が必要
企業に勤めている間は年末調整により無縁だった人が、定年退職後に公的年金等(厚生年金や国民年金)の受給者になると、原則確定申告をしなければなりません。それは、これらの収入が課税の対象である「雑所得(公的年金等)」に該当するからです。
まず確かめていただきたいのは、毎年1月に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」です。現在ははがき、電子データ(登録者が対象)で受け取ることができ、「ねんきんネット」で確認できます。
ここには、支払われた年金の合計額や、年金から源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の合計額、年金から徴収された社会保険料の合計額などが記載されています。ざっと見るだけで、1年間で受け取った年金や納めた税金などを把握することができるわけです。
一方、確定申告とは1年間の収入とその収入を稼ぐためにかかった経費、控除を基に自身の所得額と納税額を計算し、税務署に申告する手続きのこと。その結果、税金を払い過ぎている場合は還付されることもあります。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら