「ストレス=悪」の誤解が招く不調のスパイラル5つ なんでも「ストレスのせい」にしてはいけない
体調不良の原因をストレスに限定することで、問題の本質を見抜けないため、根本的な解決策を見つけることができず、いつまでも状況が解決できなかったり、同じ問題を繰り返したりする可能性がある。
このように、なんでもストレスのせいにし、ストレスさえなくなれば……と考えることで、さまざまな別の問題が生じる懸念があるのだ。
「ストレスを感じている」人が、病気になる?
米国で、約3万人の成人の動向を追跡調査した興味深い研究がある。
1998年に、「過去1年間にどの程度のストレスを感じたか」「ストレスは健康に悪いと考えているか」とインタビューしたデータを、8年後の2006年までの全国死亡率データとつき合わせて分析したものだ。
これによると、「ストレスが健康に悪い」と考えていた人たちは、他のグループに比べて死亡リスクが高かったのだ。
一方で、高いストレスを感じていたものの、ストレスを「健康の一部や成長の機会」とポジティブに考えている人たちには、死亡リスクの増加は見られなかったという。
この結果から、ストレスそのものよりも、ストレスを「悪いもの」と捉えることが、健康に悪影響を与えてしまう可能性がみてとれる。
ストレスを心配することが、逆にストレスになり、病気を引き起こし寿命を縮めているかもしれないというのでは笑えない。注意しすぎることで、かえって悪影響があるかもしれない。
ストレスを過度に恐れてしまうと、受け入れられるストレスの量が少なくなるのではないだろうか。逆に、ストレスをあまり怖がらないで、むしろ「ウェルカム!(ようこそ!)」という態度をとっていたら、それなりに大きなストレスでも受け入れられる耐性ができると思う。
このことが「ストレス耐性」といわれるものの正体かもしれない。ストレスをやみくもに避けようとするのではなく、ストレスがパフォーマンスを向上させたり、適応力を高めたりするという、ポジティブな面に目を向けることが大切だといえよう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

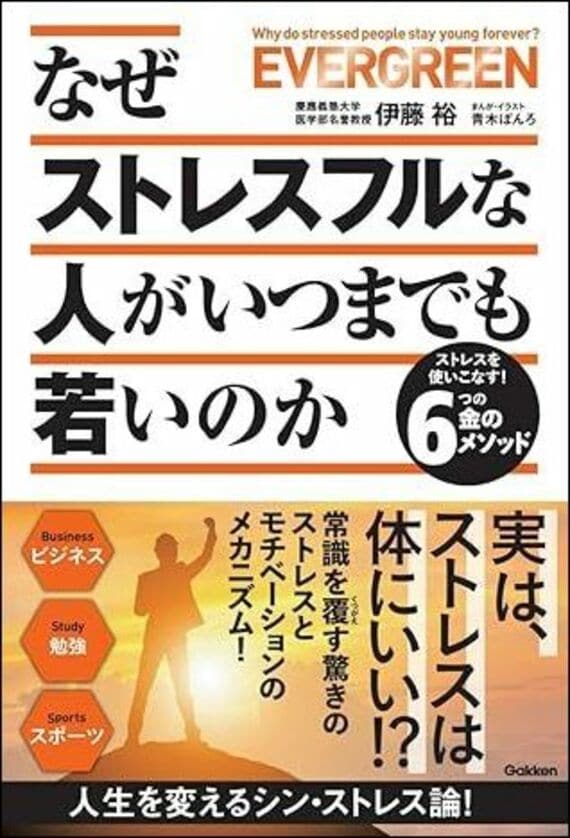






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら