堂々巡りの「石丸論法」を育んだ京大という"土壌" 結論を「出せない」のではなく「出そうとしない」
「さん」付けをしたからといって、軽く見ているわけでも、バカにしているわけでもない。反対に、それなりの敬意をあらわしていると思われる。私は、面と向かっても「さん」で呼んでいた。
ただ、なんとなく「さん」よりも「先生」と呼びたくなる、ないしは、呼ばざるをえない雰囲気を持っている人ばかりだった。実際に、「さん」で呼んでいたのは、人文研の教員以外では、社会学者の大澤真幸さんひとりだった。
飲み屋での注文は「メニューの端から端まで全部」
人文研の教員といっても、私に付き合ってもらえたのは、フランス文学者の大浦康介さん(1951年〜)だったので、一般化しづらい。
大浦さんは、稀代のフランス語の使い手で、フランス語ネイティブから「フランス人よりもフランス語がうまい」と言われていた。専門は文学理論、それも、ジェラール・ジュネット(1930〜2018年)という難しい学者の理論を読み解いていた。
また、中上健次(1946〜1992年)をフランス語に訳しており、京都大学のフランス文学者という、由緒正しい肩書きそのままの人物のように見えた。
授業に出てみると、10人にも満たない少人数相手に、そのころにフランスで話題になっていたauto-fictionをフランクに講じていたし、何より、たびたび飲みに連れていってくれた。
飲み屋さんでの頼み方は決まっていた。「メニューの端から端まで全部」というもので、学生にとってはありがたい限りで、遠慮なくたくさんいただいたし、何度もご自宅にお邪魔した。
ある冬休みには、「ロメオ」という名前の飼い犬のお守りに、鍵を預かって通わせてもらったし、私が大学を出て働き始めてからも、何度もお世話になった。
大浦さんは私ひとりを特別にかわいがってくれたわけではない(はずだ)。もっと言えば、京大には大浦さんのほかにも、彼と似たような先生がたくさんいた。コロナ禍を経た今の学生にとっては、そんな先生たちは都市伝説になっているのかもしれない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

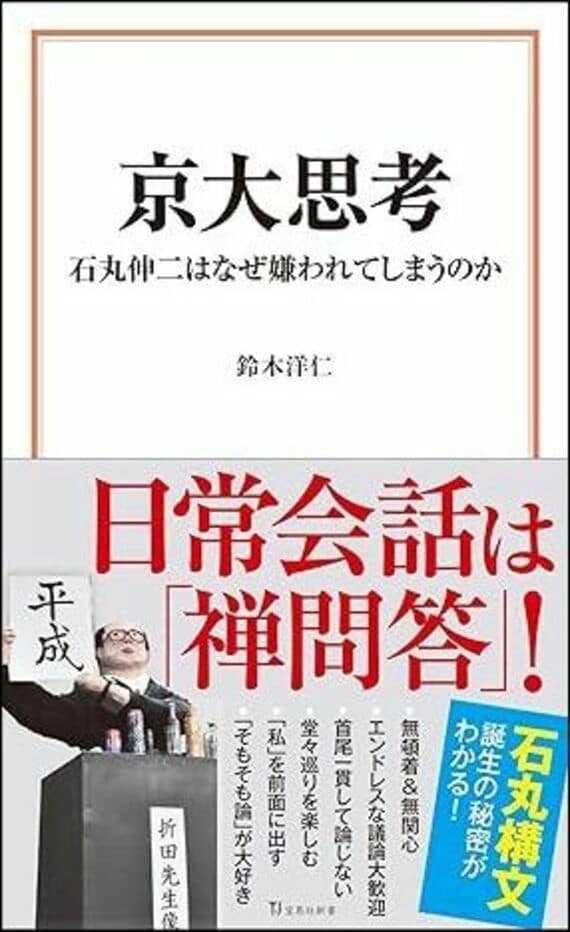































無料会員登録はこちら
ログインはこちら