東大合格者語る「解き方でわかる」伸びる子の特徴 手動かす子、じっと考える子どちらが伸びる?
また、書くことで自分の思考がどこまで進んでいるかが目で確認できます。問題を解くときはA→B→Cと段階を踏んで考える必要がありますが、たとえばAについてわかったことや考えたことを書いていったん整理しておくと、次のBに意識を集中させることができますよね。
反対に、手を動かしていなかった場合、AとBの2つを同時に頭で処理しないといけません。Bについて考えたいのに、Aのことも忘れないように一生懸命考えるのは脳の負担が大きいですよね。きっとCにたどり着く前に疲れてしまって、マンガの矢島くんのように「もういいや」と投げやりになってしまうでしょう。手を動かさずに考えるほうが楽なように見えて、実は非常に効率の悪い方法なのです。
書くことで理解度や定着度がわかる
さらに、「書く」という行為は、自分の理解度や定着度を確認するのにも役立ちます。たとえば、本を読んだり、講義を聞いた後に、吸収した内容を書き出してみる。あるいは復習として、勉強した内容を何も見ずに書き出してみる。もし本当に理解や記憶ができていれば、すらすらと手が動くことでしょう。
反対になかなか手が動かないならば、まだ定着が不十分だといえます。何をどの程度覚えたり理解しているのかが一目瞭然で、ごまかしが利きません。そのため、「何となく覚えたつもり・わかったつもり」を防いで、復習すべきポイントがすぐに見分けられるのです。
このように、手を動かすか否かで、勉強の効率は大きく変わります。頭で考えるだけで済まそうとするのは、避けたほうがいいでしょう。勉強で結果を出したいという人は、ぜひ参考にしてみてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

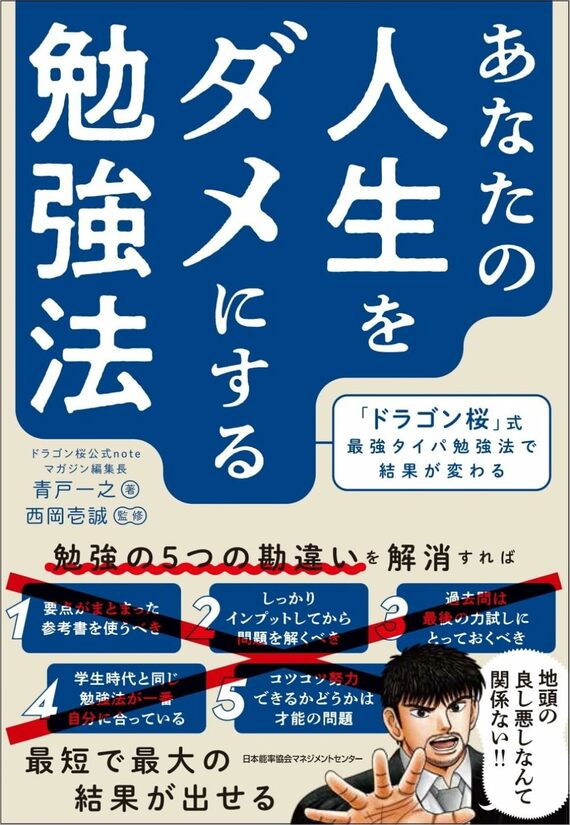

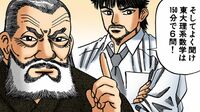




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら