「長いことお目に掛からないうちに、びっくりするほど大人っぽくなりましたね」と、ちいさな几帳(きちょう)の帷子(かたびら)を引き上げて顔を見ると、恥ずかしそうに横を向くその姿は、非の打ちどころがない。灯火に照らされた横顔、髪のかたちも、心のすべてで慕っているあの方とまったくそっくりではないかと、光君はうれしくなる。紫の姫君に近づき、会えずにいて気掛かりだったあいだのことをあれこれ話した後に、
「これまでにあったことをゆっくり話してあげたいけれど、縁起が悪いようにも思うから、少しあちらで休んでからくるよ。これからはずっとそばにいるから、私のことが嫌になるかもしれないね」と、こまやかに話して聞かせる。それを聞いて少納言はありがたく思いながらも、やはり不安を感じずにはいられない。お忍びでお通いになる尊い身分の女性たちがたくさんいらっしゃるのだから、いつ紫の姫君のかわりとなる厄介な姫君があらわれるかと心配でならないのだが、……それもずいぶん憎たらしい気のまわしようだこと。
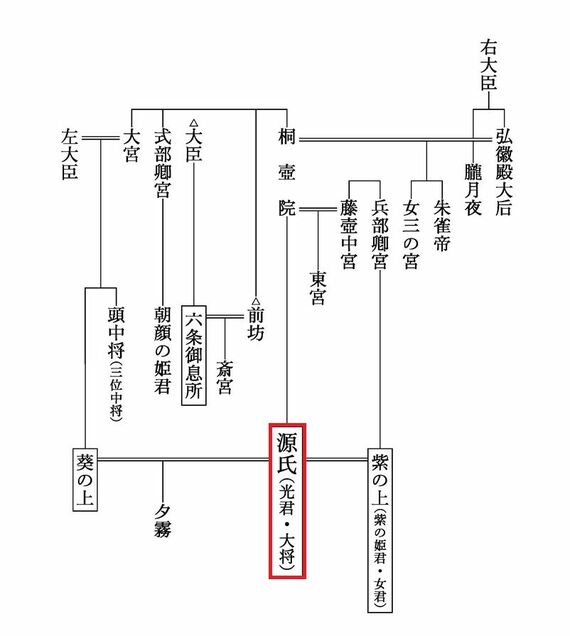
もの思いにふけることが多くなり
光君は自分の部屋に入り、中将の君という女房に足を揉(も)んでもらっているうちに眠りに落ちた。翌朝には左大臣家にいる若君に手紙を送った。受け取った左大臣家からは悲哀のにじむ返事が来て、光君は悲しみの深さを思い知らされる。
光君は、もの思いにふけることが多くなり、忍び歩きもだんだん億劫になって、出かけようともしない。紫の姫君は何もかも理想的に育ち、女性としてもみごとに一人前に思えるので、そろそろ男女の契りを結んでも問題はないのではないかと思った光君は、結婚を匂わすようなことをあれこれと話してみるが、紫の姫君はさっぱりわからない様子である。
することもなく、光君は西の対で碁を打ったり、文字遊びをしたりして日を過ごしている。利発で愛嬌(あいきょう)のある紫の姫君は、なんでもない遊びをしていても筋がよく、かわいらしいことをしてみせる。まだ子どもだと思っていたこれまでの日々は、ただあどけないかわいさだけを感じていたが、今はもうこらえることができなくなった光君は、心苦しく思いながらも……。




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら