人を不幸にするガバナンスの不条理から脱却を。

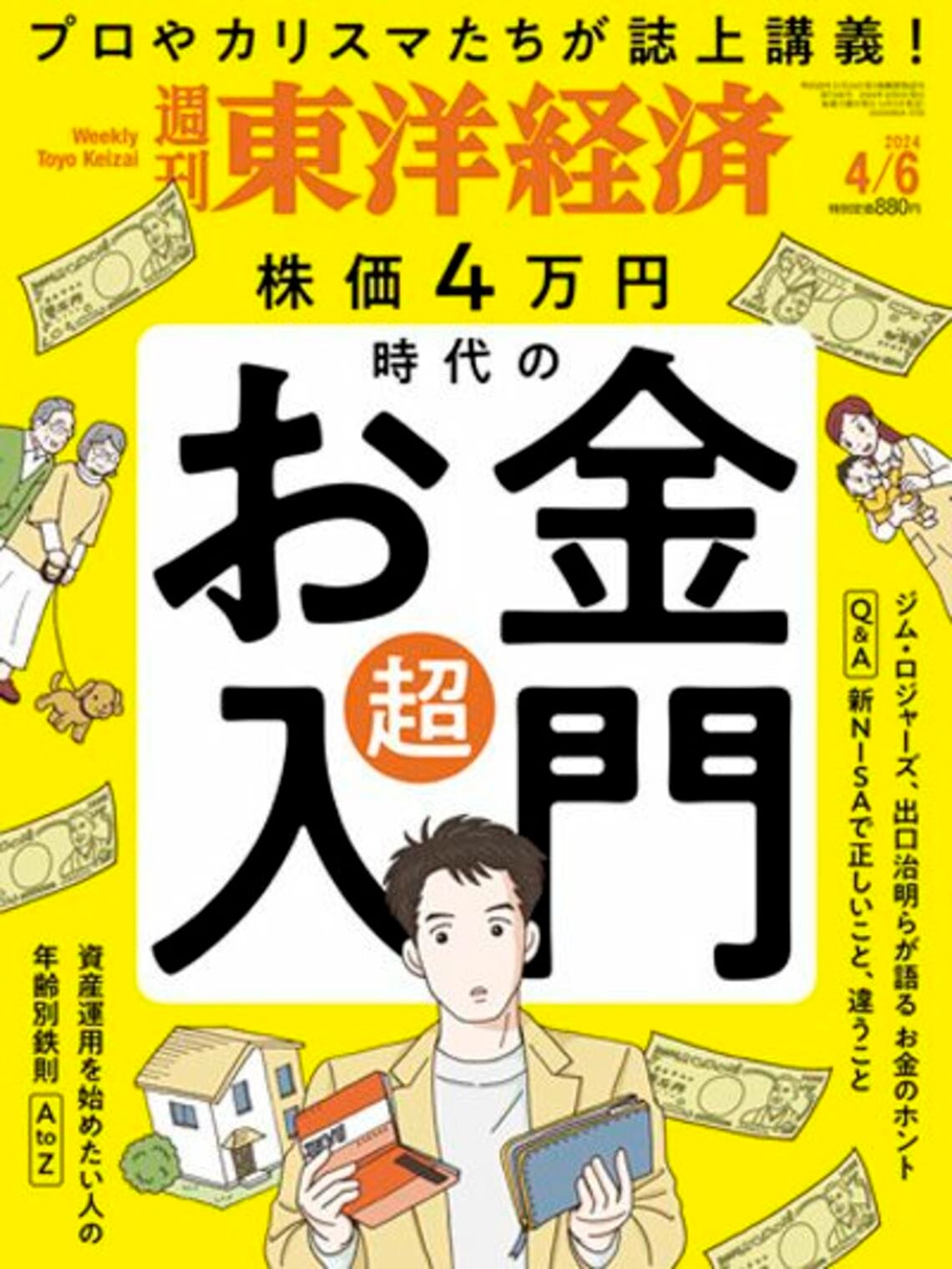
初めに断っておくが筆者はコーポレートガバナンス不要論者ではない。コーポレートガバナンスには「衰退型」と「成長型」があり、前者はすべての人を疲弊させるうえに利害関係者への責任も果たせないという主張をしたいだけだ。
本稿後半で「コーポレートガバナンスとは何か?」「日本の組織のコーポレートガバナンスはどこに向かうべきか?」について、誰でも理解しやすい原理原則論から説明していく。まずは漠然としたコーポレートガバナンスのイメージから話を進めていく。
多くの会社において、コーポレートガバナンスは政府をはじめとした「お上」から押し付けられる、「名ばかりガバナンス」という認識だろう。会社の実務を何もわかっていない官僚たちが、無駄な会議と無駄な書類を求めてきて、会社の成長に手かせ足かせをはめてくる……という具合だ。
無意味な仕事を増やす
実務を知らないお上に従うほど会社もバカではない。
面従腹背で、体裁を取り繕うために役員会は性別、国籍、職歴などを多彩にしつつ、実際は同じ考えのゴルフ仲間でそろえ、法の抜け穴を突き、誰も読まない管理書類はテンプレのコピペとAI(人工知能)利用で一丁上がり、流行に乗って「制度は賢くハックする」の精神だ。
組織内で無意味な仕事を増やしているのだから、付加価値生産性など上がるはずもない。こうして「表面上はコーポレートガバナンスの優等生だが、資源を浪費するだけのジリ貧な組織」の出来上がりである。この状態に陥っては、資源の出し手はおろか、経営者もまた苛烈に経営責任を追及されるリスクを負う。

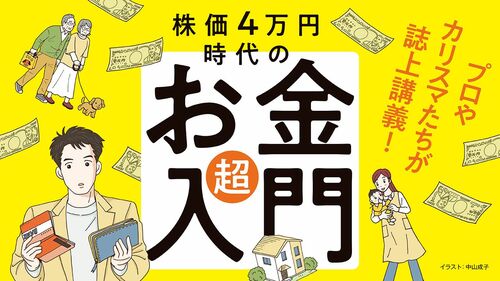

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら