女もさすがに不思議に思い、光君からの使いの跡をつけさせたり、夜明けに君が帰る時の道筋をさぐらせたり、住まいを突き止めようとするが、光君はいつもうまく彼らを撒(ま)いていた。そのくせ、逢わずにはいられないほど相手の女に惹(ひ)かれていた。こんな粗末ななりでお供もつけずに通うとは、貴人としてあるまじきことと苦しく思いながらも、気持ちとは裏腹に光君の足は女の元へ向かうのである。
恋をすれば、真面目な男でも我を失うこともある。光君は、そんなふうにみっともない失態だけは演じまいとずっと自重し、今まで世間から非難されるような振る舞いをしたことはなかった。それが今度は奇妙なことに、今別れてきたばかりの朝でも、日が暮れればすぐ逢える昼でも、女に逢いたくて気が気ではなく、苦しいほど女のことを考えてしまう。なんとももの狂おしく、こんなに夢中になるほどの恋ではないと気持ちを静めようとしてみる。女は、なんとも言えず素直でおおらかではあるが、思慮深いわけでもなくしっかりしているわけでもない。まったく初々しい少女のようでいて、しかし男女のことを知らないわけではない。それほど身分の高い姫君というわけでもない。この女のいったいどこにこれほど惹かれてしまうのかと、光君はくり返し考える。
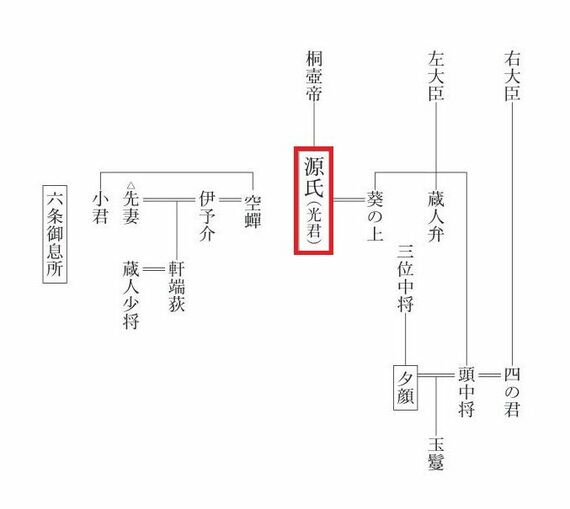
ふつうの恋とは違う悩みに取り憑かれ
光君は従者が着るような粗末な狩衣(かりぎぬ)を着て、顔も隠して、夜が更けて人が寝静まるのを待ってから出入りしている。まるで昔話によく出てくる化けものじみていて、女は気味が悪くなるが、しかし、暗闇の中で触れると、その手触りで、男が並の男ではないことがはっきりとわかるのである。
いったいどこのどなたさまなのかしら、やっぱりあの浮気男があれこれ手引きをしたに違いないわ、と惟光を疑うが、惟光はしらを切り、とんでもないとでも言いたそうに、自分の恋に夢中になっているふうなので、どういうことなのか女にはさっぱりわからない。そんなわけで女は、ふつうの恋とはまったく違う悩みに取り憑(つ)かれ、男のことを思うのだった。
心を預けてくれたように見えるこの女が、あるときふいに行方をくらましてしまったらどうしよう、と光君は考える。どこをさがしていいものやら、見当もつくまい。今の住まいはどう見ても仮の宿としか思えない、だからいつどこへ移ってしまうか予想することもできない。追いかけようとして見失ってしまい、それきりあきらめがつくのならば、その程度の気まぐれな恋として忘れられようが、そんなふうに終えられるようには思えない。





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら