小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
「捨てましたか?」と検査を注視していた細川が振り向く。
「ああ」と答えながら、小刀がなるべく見つからないよう、着替えの長衫(チャンシャン)に包(くる)んで鞄の底に押しこむ。
細川はこの行為に気づいていないようだ。鞄の中身を検(あらた)めながら、はたしてこの小刀に命を懸ける価値があるのだろうか、と自問する。
この行為は勇敢なのか、それとも臆病なのか。
少なくとも卑怯ではあろう。自分は今、ロシア兵だけでなく細川も騙そうとしている。
高木の隣にいた男が呼ばれた。まだ小刀を捨てる時間が残されていたが、鞄の中の配置を変えて、小刀が見つかりづらいように細工することにした。前の男への検査の仕方を見ても、ロシア兵は着替えの中まで詳細に見ようとはしていない。この隠し方で十分ではないか。命も助かるし、誇りも守られる。それでいいではないか。
認めよう。自分は命と小刀の価値を天秤にかけたわけではない。鞄に隠せば小刀が見つからずにすむのではないか、という可能性に賭けただけで、天秤に至ってすらいない。
隠蔽の作業を終え、ハルビンの街並みを眺めながら座っていると肩を叩かれた。ロシア兵だった。
「お前は日本人か?」
「そうです」と高木の代わりに細川が答える。
肩を叩いた男が、他の男を調べていた別のロシア兵を呼びにいき、三人組がやってきた。先頭に立った一等立派な軍服を着ていた上官風の男がこちらを指さし、怒鳴るような声で何かを喋(しゃべ)った。高木も簡単なロシア語ならわかったはずだが、彼が何を言っていたのかは理解できなかった。細川が何かを怒鳴り返した。後ろに立っていた若いロシア兵が細川に銃口を向けた。
「やめてください」とロシア語で口にした細川がこちらを向いた。「彼らは、僕たちが間諜ではないかと疑っていて、何か身分を示すものはないか、と言っています」
銃口が向けられた
高木が「わかった」としゃがみこみ、鞄を開けた瞬間、細川に向いていた銃口が自分に向くのを感じた。
戦場に立ったことはない。敵意を持った相手に銃口を向けられたのは初めての経験だった。両手が震えていた。その瞬間まで松花江の底に沈んでいた死の顔が、突然こちらを向いたようだった。やめてくれ、爆弾を出すわけじゃない。そう叫びたい気持ちを堪(こら)え、あてどなく鞄を探る。思うように頭が働かなかった。書状をどこに入れたのか、すぐに思い出せずにいた。ほんの数秒が数時間に感じられた。
あった。
やっとの思いで、高木は鞄からウラジオストクの知事にもらった書状を出した。上官は書状を奪うように取り、しばらく読んでから何かを言った。
「『本物かどうかわからないので、一度預かる』と言っています」
「わかった」と高木は答える。
上官が後ろの二人に「鞄を調べろ」と指示を出し、高木のわからないロシア語で何かを言いあう。
部下の一人が高木の丸型鞄の中身を、乱暴に放り出して甲板に広げた。どうなっている、話が違う、と叫びそうになる。他の労働者に対してはそういった調べ方をしていなかった。
鞄の底に丸めていた長衫(チャンシャン)が甲板に転がる。
「日本人の乗客は特に念入りに調べるみたいです。もしかしたら、先人から何かまずいものが見つかったからかもしれません」
細川はそう言った。




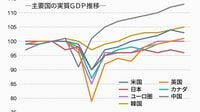


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら