小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
高木は懐の小刀を握りしめた。この小刀が──一度も会ったことのない父の武士の血が──高木を軍人にさせた。そして、今も軍人でいさせてくれていた。
視線の先に、誰かが投げ捨てた木箱が浮かんでいる。細川の父は若い女性とああやって浮かんだ漂流物につかまり、そうして命を永らえたのだろうか。木箱が沈めば己の命はない。松花江に捨てられた死体と同じように、深い水の底に沈んでいくだけだった。
「運よく救助船に見つけてもらい、父と女性は助かりました」
細川は足元の鞄を持ちあげながら言った。「お互いの名前を教えあうこともなく、二人はそのまま別れました。そしてそれから七年後、銀座で商談相手との酒席を終えた父は、街でその女性を見つけたんです」
「奇跡のような話だな」と高木はつぶやく。
「そうでしょうか」と細川が言う。「そのまま父と女性が結ばれれば、たしかに奇跡のような話でしょう。当然ですが、そんなことは起こりえませんでした」
「何があったんだ?」
「父は女性に声をかけました。あのとき海で一緒に漂流した男です、と。ええ覚えています。女性はそう答えたそうです。その折は大変でしたね、波も高くて、という立ち話を五分ばかりして、『では』と別れました。母の出産が近かったので、時間がなかったそうです。そうして父が家に帰ると僕が生まれていて、母が死んでいました。父は、自分がもっとも死に接近したとき隣にいた女性と会い、その日に妻を亡くしました。父はそれが何か不吉な符丁だと感じたそうです。お前にも、死の符丁がなければいいのだが、と言われました。僕の知っている母の話はこれがすべてです。母がどんな人で、どんな顔だったのかも知りません」
ハルビンはもう目と鼻の先だった。
これは奇跡なのでしょうか、と細川が言う。わからない、と高木は首を振る。たしかにそれは、細川という人間の出自に影を落とす「不吉な符丁」かもしれない。奇跡とはもっと、祝福された何かでなくてはならぬ。
そういえば、書状をもらったとき「ハルビンは奇跡の街だ」とウラジオストクの知事が言っていた。数年前まで何もなかった荒野に、我らロシアはひとつの都市を造ったのだ。鉄道を敷き、河口に港を造り、赤煉瓦で官府を建て、立派な兵舎を置いて街区を三つにわけ、それぞれの用途を決めた。そこにロシアから、清から、朝鮮から商人が集まり、その街は今も大きくなっている。君たち日本人に、そんなことができるのか。
できないと思います、とそのとき高木は答えた。眼前に広がるハルビンの西洋風の街並みを眺めながら、やはりできないだろう、と思う。大陸を貫く鉄道に、煉瓦造りの巨大な官府。莫大な資本と資源、そして労働者と技術。あれは間違いなく、西洋の都市だった。
ロシアの物流の要衝・ハルピン
乗合船は減速をしながら河岸に近づいていた。高木は松花江の着発線を見た。線路が引きこんである。中央停車場から汽車がそのままやってこられるようになっているからだろう。数十人もの苦力たちが、積み荷を貨物列車から着発線に運んでいる。遠くモスクワから届いた物資をブラゴヴェシチェンスクやハバロフスクへ送るためである。この船には火薬や鉄が積んであった。軍用と鉄道用だ。これらの物資を東清鉄道で内陸へと輸送していき、守備隊の強化と路線の延長に使うのである。




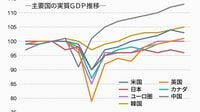


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら