小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
「妙に陽気だが、甲板にへばりついていたのではないのか?」
「今も吐きそうですよ。暑いし、正直なところさっさと日本に帰りたいです。でも王さんの面白そうな話が聞こえたので」
支那人のくだらない言い伝えのどこが面白いのだろうか、と呆れながら「出身だったな」と答えた。「生まれは薩摩(さつま)だが、東京で育った」
「ご両親が薩摩なんですか?」
「そうだ」と高木はうなずいた。父は高木が生まれる前に西南戦争で亡くなっていた。十五歳のとき、形見の小刀を母から譲ってもらい、それ以来肌身離さず持っている。臆病な人だったから死ぬことはないと思っていたのに、戦場で人が変わってしまったのかしら。母はそう言っていた。
今となっては、高木は「そうではない」とわかる。自分も父に似て臆病だ。だが臆病だからこそ死ぬこともある。今回の任務もそうだ。危険なのはよくわかっていたが、高木は断れなかった。断るだけの胆力がなかった。
「僕の母も薩摩なんですよ」
「今も薩摩にいるのか?」
「いえ、僕を出産したときに亡くなってしまったので」
「そうか」
高木は最近よく、死んだ父のことを夢に見ていた。顔を見たこともなかったが、どういうわけか、ときおり戦場に立った父の姿を幻視するのである。敗勢になり、敵の刀で血だらけになった父に「前へ出ろ」という命令が下される。父はもうすぐ生まれる息子のことを思い「嫌だ」と叫びたくなるが、それでも前へ出てしまう。起きてからいつも考える。はたしてそれは勇敢ゆえの行動だろうか。それとも臆病さのせいだろうか。
父から聞いた母の思い出
「一度だけ、父に母のことを聞いたことがあります。父はこう言いました──」
細川がそう口にしたとき、遠くにうっすらと建物らしき影が見えた。隣にいた支那人が「到了(タオラ)!」と叫び、甲板の中央にいた人夫たちが一斉に外柵に殺到した。そこら中から「ハルビン」という声がした。ついに到着したのだ。
細川は気にせず話を続けていた。「貿易商だった父は、買いつけや商談のために船でいろんな国を回っていたそうです。米国へ行った帰りに、横浜の沖合で船が座礁して海に放りだされました。救助を待つ間、木材につかまり太平洋を漂っていると、溺(おぼ)れかけていた若い日本人女性を見つけました。彼女の手を取り、大きな木板に一緒にしがみついて、二時間ほど漂流しました。そのとき『助かったら今度は陸上で会いましょう』という話をしたそうです」
何かの儀式だろうか。後ろでは支那人たちが河へ向かってさまざまな所持品を投げこんでいた。空き瓶や食糧、何かの紙もあれば、大きな巾着袋をそのまま捨てている者もいた。高木の目に眩(まばゆ)い光が走った。誰かが捨てた金属のナイフが日光を反射していたのだった。ナイフは音も立てず、河に沈んでいった。




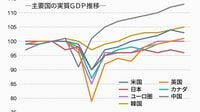


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら