小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
死体を見るのは初めてだったんです──細川はそう口にしてからずっと、地蔵のようにじっとうずくまっていた。生きているのか死んでいるのかわからなかったので、たまに確認するために肩を叩いた。その度に細川は目玉だけ動かしてこちらを見た。恨むわけでもなく、助けを求めるわけでもない、ひどく乾いた視線だった。そんなとき、高木は「お前がここで死んだら、せめて俺の手で河に沈めてやる」と声をかけるのだった。
「『燃えない土』があるということは、『燃える土』もあるのですか?」
細川がいつの間にか隣に立っていて、厚い眼鏡が支那の陽射しに光っていた。雰囲気が妙に明るく、死を目前にした人間が最後の炎を焚きあげ、急に明瞭になっているようにも見えた。
「無理をするな。次はお前が河に捨てられる番だぞ」と高木は睨みつける。細川は「大丈夫です」とにやにやしている。
「いいか、日本人(リーベンレン)」と、ほつれた長い辮髪(べんぱつ)を巻きとりながら王が語りかけた。「土には三種類ある。一番偉いのが『作物が育つ土』で、二番目が『燃える土』。どうにも使い道のないものが『燃えない土』だ。『燃える土』は作物を腐らせるが、凍えたときに暖をとれる。だが、『燃えない土』はどんな用途にも使えない。死体も同じことだ」
「はじめて聞きました。とても面白い話です。王さんはどこの出身なんですか?」
高木には一度も見せたことのない、好奇心にあふれた表情で細川が質問している。
「出身は山西だが、今は奉天の東にある李家鎮(リージャジェン)という村に住んでいる。俺は漢人でな。桃源郷があるって話に騙されて、東北(トンペイ)に移住したんだ。俺の母さんは小作人をやっていたんだが、収穫した大豆を全部取りあげられて、鶏の骨みたいに痩せ細って死んでいったよ。日本人、お前の両親は何をしてるんだ?」
「母はいません。父は貿易商をしています──」
細川と王はまだ話を続けていたが、高木は丸型鞄を両手で抱え、船首まで歩いていった。土は作物の役には立つかもしれぬが、戦争の役には立たない。興味を引かぬ話だった。
船での決まりは簡単だった
甲板からはずいぶん人が減った。途中で下船したり、死んで船から捨てられたりした者がいたおかげだ。
この船での決まりは簡単だった。むやみに他人の領土を侵犯しないこと。死体は腐る前に近くの者が捨てること。寝転がっている者を踏まないこと。他人の喧嘩にはなるべく関与しないこと。外交と同じであるから覚えやすい。
暇つぶしの手段は、寄港中に買うことのできる、隅田川のドブみたいな味の酒を飲み、我を忘れることくらいだ。大陸の強い陽射しに抵抗する手段は一つだけ──我慢すること。どれだけ暑くても甲板に日陰はないし、船室には隙間なく貨物が積まれているので、乗客は立ち入ることができない。
日中はみなじっとして、暑さを頭から締めだす作業に没頭している。乗客同士の会話などほとんど存在せず、騒ぎがあれば大方は場所取りに関する揉めごとだ。それ以外は「船が前の港を出て何日経ったか」、そして「次の港まで何日かかるか」、それくらいである。




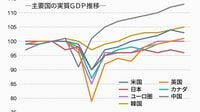


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら