小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
誰も来なかった。部屋の外に誰かいるのかもわからなかった。扉を開けようとしたが、頑丈に鍵がかかっていた。
どれくらい時間が経ったのかわからない。
首を絞めてみようと、脱いだルパシカを捩(ねじ)り、机に巻きつけていたときだった。
足音が聞こえ、解錠とともに扉が開いた。立っていたのは初老のロシア人だったが、軍服ではなく平服だった。
「何をしてるんですか?」とその男がロシア語で聞いてきた。高木は質問の意味がわからないふりをした。
「その机では自殺できませんよ」
男の後ろから声が聞こえた。日本語の、聞き覚えのある声だった。
「そうなのか?」
「簡単な力学です。首を絞めたとき上下に力が加わるので、机の脚では安定しません。仮に椅子に引っ掛けても、固定する位置が低すぎます。死ぬなら《ここ》です」
細川が扉の取っ手をつかんでいた。
「命より大事なんでしょう?」
「大丈夫だったのか?」
「なんとか」と答え、細川が部屋に入ってきた。「朗報が二つあります」
「なんだ?」
「奉天の東、李家鎮(リージャジェン)という村の付近に資源があるかもしれません。ハルビンの任務が一段落したら、一度調べに行く必要があるでしょう」
「どうしてそんなことを知っている?」
「乗合船にいた王(ワン)という労働者ですよ。彼が『燃えない土』の話をしていたでしょう。李家鎮では土が燃えるんです。石炭が混じっているからでしょう。ロシアも清朝もそのことに気づいていません。周辺にはまだ炭鉱がないそうですから」
「もう一つは?」と聞くと、細川は胸元から小刀を取りだし、高木の手のひらに押しつけた。
「どうしてこれを?」
「命より大事なんでしょう?」と細川が笑った。「実は、これを取り返すのにかなりの時間がかかったんです」
高木が何かを言う前に、細川が「僕はホテルに帰って寝ます」と言った。「軍人たちを説得するのに体力を使い果たして、くたびれて死にそうです。夕食をとりたいなら、そのロシア人に付いていってください。ハルビンで任務を終えたら、李家鎮の調査をしましょう」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら





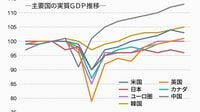


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら