小説『地図と拳』が描く日露戦争前夜の緊迫情景 「序章」を全文公開、男はロシアの根拠地に渡った
移動中に兵士の一人が「ロシア語はわかるか」と聞いてきたが、高木は言葉が通じていないふりをした。二人の兵士はいくつかロシア語の質問をしてから会話を諦めた。「こっちだ」と身振りで示し、船着場から街の中を進む。一人は常に銃口をこちらに向けていた。
十五分ほど歩いた先にある赤煉瓦の建物に入り、高木は小さな部屋の中に放りこまれた。その部屋でもロシア語で執拗に質問された。「ナイフを隠し持っていた男は誰だ」という質問と、「お前たちは何のためにここへ来た」という質問である。高木は何を聞かれても「私は高木です」という言葉と、「日本の茶商人です」という言葉以外は発しなかった。二ヶ月の留学でロシア語はいくらかわかっていたが、最初にわからないふりをしてしまった以上、突然話しはじめるのも不自然だろうと思った。
会話を諦めたロシア兵が部屋から出ていき、外から施錠されると一人になった。
小さな部屋の中で、自分がどうするべきか考えた。
「あれは私のナイフです」とロシア語で説明するべきだろうか。細川は身代わりになってくれただけだ、と。しかしその言葉にどれだけの意味があるのだろうか。自分の命に、細川の代わりとなるだけの価値があるとも思えない。自分だって、先人たちと同じようにいずれ処刑されるのだろう。
どこまでも臆病で、卑怯な人間だ
もちろん、彼を助けてほしいと嘆願することはできる。だが、それが有効であるとも思わない。そもそも、自分がロシア語を話すべきではないとも思う。細川はロシア語の通訳だと説明しているだろう。もし自分がロシア語を口にしてしまえば、その主張が受け入れられづらくなるかもしれない。
どうして細川は身代わりになってくれたのだろうか。彼は軟弱なインテリ学生で、「燃えない土」なのではなかったか。しかし実際には、軍人である自分よりもずっと勇敢だった。自分は細川を欺(あざむ)いていた。そのことが発覚しても、彼は迷いがなかった。自分は「そのナイフは私のものだ」と口にすることもできなかった。危険だとわかっている軍刀を捨てることすらできなかったし、その軍刀を捨てることができなかったと白状することもできなかった。どこまでも臆病で、卑怯な人間だ。
任務に失敗は存在しない。かつて、士官候補生時代に上官が言っていた。任務とは、成功するか死ぬかのどちらかである。高木はどうやれば死ぬことができるのか考えた。ロシア兵は今、必死になって日本語の話せる者を探しているのだろう。通訳が見つかれば、高木にも拷問が始まるに違いない。今は自決する最後の機会だ。だが部屋に備えつけられた椅子と机で、うまく死ぬことができるのだろうか。士官学校ではこういった状況で死ぬやり方は教わらなかった。武器はない。ピストルは河に捨てたし、小刀は細川とともにどこかへ消えた。




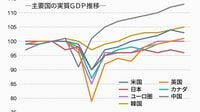


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら