退職した人は16%「不妊治療」調査で見えた過酷さ 医師から見た「働きながら不妊治療」の現実

都府県をまたいで通院している人も
今回の不妊治療の保険適用によって、患者さんの経済的負担を減らすことができるようになりますが、不妊治療のハードルは費用面だけではありません。
2020年の末、厚生労働省の特別研究でコロナ禍での不妊治療の実態を検討するため、私が所属する山王病院と福岡県の高木病院、京都府の田村秀子婦人科医院の3施設に通院中の患者さんを対象にアンケートを取りました。
768件に上る回答から見えてきたのは、コロナ禍かどうかにかかわらず、通院するための時間を確保することの難しさや仕事との両立に対する悩み、そして精神的負担でした。
施設所在地と患者居住地をみると、同一都府県内の受診は64%。実に36%の患者さんが、不妊治療の受診のために都府県をまたいで通院をしているのです。不妊治療の期間や通院回数を考えれば、これは大変な負担です。
不妊期間の長さは1~3年が39%(297件)で最多でしたが、中には10年以上にわたる人も6%(43件)いらっしゃいました。福岡と京都の施設では、患者さんの年齢は35~39歳が最多だったのに対し、東京にある山王病院では40~45歳が最多。また、女性の職業勤務形態は3施設ともフルタイム勤務者が約6割を占めていました。


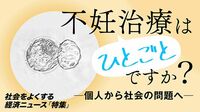






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら