黒船「OYO」、不動産賃貸の手痛い挫折が残す教訓 DXの「理想」に立ちはだかった「現実」のハードル

競争を勝ち抜くカギは、「われわれが不動産のビジネスをより深く理解している」(緒方取締役)点にあるという。
霞ヶ関キャピタルの本業は物流施設やホテルの開発・ファンドの組成だ。「不動産業のデジタル化には技術だけでなく、リアルの不動産ビジネスも理解する必要がある。非効率な商慣習があったとしても、それが現在まで続いているのには理由がある。(IT畑の)OYOには理想と現実のギャップがあった」(同)。
OYOの不動産賃貸事業を受け継いだKC technologiesには、不動産系のスタートアップ2社も共同で出資する。このうちの1社であるKeeyls(キールズ)は、賃貸住宅の鍵の受け渡しを、コンビニなどを通じ無人で行えるサービスを提供している。
管理会社や仲介会社の協力を仰ぐことも重要
キールズの大貫功二代表取締役CEOは、「不動産業に関わる当社の強みは、投資家、管理会社、仲介会社、入居者といった各ステークホルダーの収益構造を理解していることだ」と話す。
「デジタル化によって業務が楽になったからといって、その分をすべて手数料として徴収するのではなく、各者にどう配分するかを考えることで、不動産業界の(デジタル化への)理解も得やすくなる」(大貫CEO)。
同じくKC Technologiesに出資するプロフィッツは、不動産ファンドの企画や組成を手掛ける企業だ。同社の田中慎一郎代表取締役は、「デジタル化はわれわれだけでは推進できない。管理会社や仲介会社の協力を仰ぐことも重要」と話す。
OYOは2年間の事業を通じて、理想と現実の間に立ちはだかる壁を教訓として遺した。一方で、DX(デジタルトランスフォーメーション)への要求はどんな業界でも高まっている。保守的な不動産業界と進歩的なテック企業という二項対立から脱却し、リアルとデジタルを融合できるかがOYOの「第2の創業」の正否を左右する。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


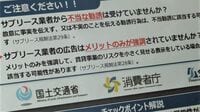






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら