黒船「OYO」、不動産賃貸の手痛い挫折が残す教訓 DXの「理想」に立ちはだかった「現実」のハードル
そこで、自社物件を対象にスマホ上で入居手続きが完了するプラットフォームを構築。気軽に入退去ができることをウリに、生活の拠点を転々とする新しい生活スタイルを提案した。ソフトバンクグループからの出資も追い風に、「全国100万室を確保する」という野心的な目標を掲げた。
営業員には借り上げ戸数をノルマとして課し、2019年夏頃は「OYOがいちばん高く借りてくれる」と物件オーナーはバブルに沸いた。首都圏約1000戸から始まった管理戸数は、ピーク時に8000戸以上にも達した。
だが採算面では赤字が続き、ほどなくして軌道修正を迫られる。デジタル化の「戦略」こそ業界に先んじていたOYOだったが、物件確保のための「戦術」に誤算があった。
徐々に「旧来型の不動産業」の色彩に
OYOはプラットフォーム上に各不動産会社が物件を持ち寄る形ではなく、OYO自らが借り上げた物件を載せていく形でサービスを展開した。入居者に対しては、OYOがサブリース(転貸)を行う形だ。
空室時にも家賃負担が発生するサブリースをあえて採用した理由は、転貸を通じた利ザヤの獲得だけではなかった。
OYO側で物件を借り上げれば、室内の家具家電やインテリア、公共料金の契約に至るまでOYOが管理できる。外部企業と提携して入居者限定のサービスや商品のサンプリングを展開したり、利用状況をビッグデータとして収集したりすることで、新たな事業展開につなげる目論みもあった。
ところが、物件数拡大を急ぐあまり、駅から遠い物件や高値掴みで借り上げた物件も多く、伸び悩む稼働と重い家賃負担に苦しんだ。2019年末頃からは不採算住戸の整理へと舵を切り、ビジネスモデルの抜本的な見直しを強いられた。
自慢だった契約手続きのデジタル化も、現場では試行錯誤が繰り返されていた。「最近はこんなものまで持ち歩いている」。2019年末の取材当時、OYO社員(当時)がカバンからおもむろに取り出したのはスリッパ。「室内を見てから決めたいという人が思いのほか多く、(リアルの)内見サービスを導入した。手続きはすべてスマホで完結するのだが……」(同)。
入居者の募集についても、自社プラットフォームだけでなく不動産仲介会社にも依頼するなど、徐々に旧来型の不動産業の色彩を帯びていった。


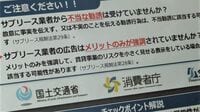






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら