米国で学んだ日本人留学生たちの共通点とは?
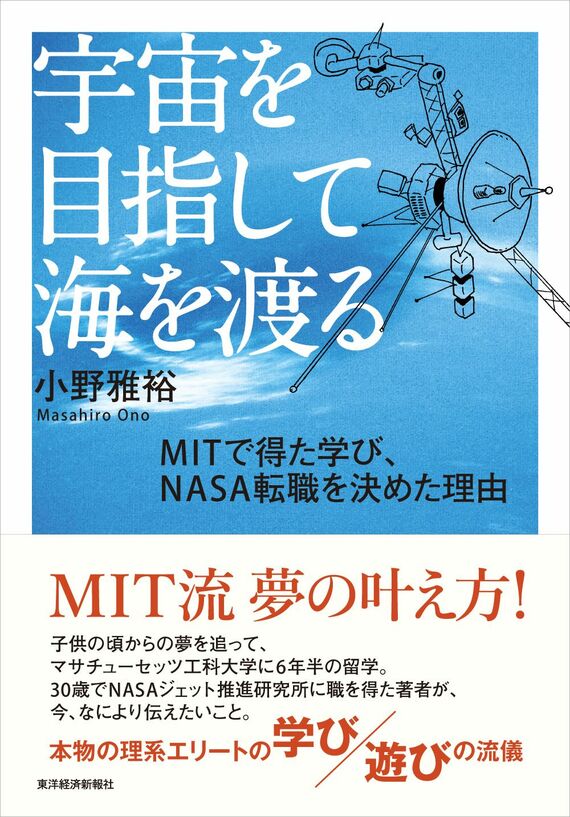
僕がMITの学生だった頃、同じく学位留学をしていた日本人の仲間たちと酒を片手に身の上話をよくした。
そこで気がついたのは、彼らのうちで、親の海外赴任で子どもの頃に海外に住んだことがあったり、また、親に留学経験があったりする人が比較的多いということだった。
僕もそうだった。子供の頃、食卓で両親が楽しそうに話していたことといえば、決まってアメリカ時代の思い出話だった。
僕も一緒にアメリカにいたはずなのだが、赤ん坊の頃だったので、記憶も英語もひとかけらも残っていなかった。
だから僕の脳には、「アメリカって楽しいんだろうなあ」というあこがれだけが、記憶を伴わずに焼き付いた。その後に僕がMITに留学した理由は、意識的には宇宙工学を究めたかったからなのだが、無意識的にはこの幼少からのあこがれがあったのだと思う。
著書には僕の家族が頻繁に登場する。それは親の自慢をしたかったわけでも、妻とのノロケ話をしたかったからでもない。単純に、今の僕を、彼らなしには語ることができなかったからだ。とりわけ両親からの影響は絶大だった。反抗期の頃は親みたいには決してなりたくないなんて思っていたのに、今になって振り返ってみれば、僕はあらゆる面であの親の子だと痛感するのだ。本稿では、著書には書ききれなかった家族の話をしようと思う。
あたかもアメリカ行きが決まっているかのように

父は大手電機メーカーに勤めていて、結婚し僕が生まれた直後、社費留学の機会を得た。
もう少し詳しく書くと、彼は結婚前、まだ社内選抜を通っていなかったにもかかわらず、あたかもアメリカ行きが決まっているかのように話して母の気を引いた。
母は高校で英語教師をしていたので、英語を教えてほしいというのをデートに誘い出す口実に使った。母にも若い女性らしい海外へのあこがれがあったのだろう。父の作戦が奏功して、両親は結婚し、母のお腹に僕が宿った。
僕がオギャーと生まれ、父がその瞬間に立ち会い損ね、母の特大のカミナリが落ちたのが1982年。その数カ月後、父は一足先にアメリカへ旅立った。アリゾナ州のツーソンという、砂漠のど真ん中にある街だった。家のトイレにタランチュラが出没するような場所である。
アリゾナ大学は日本では有名ではないかもしれないが、父の専門である光学では世界でトップレベルの学校だ。そこにいる大物教授の下で研究をするのが留学の目的だった。

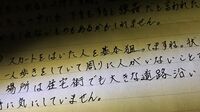































無料会員登録はこちら
ログインはこちら