ナポレオン時代のヨーロッパの複雑な政情に深くからんだ『ラ・トスカ』の物語を、円朝は実に見事に日本に置き換えている。重要な小道具となる『ラ・トスカ』の伯爵夫人の扇も、毬信のなじみ芸者の扇子に置き換えられ、女主人公の嫉妬心を煽りたてる機能をうまく果たしてまったく違和感を感じさせない。心理描写も見事であり、かの正岡子規をして「小説の趣向かくこそありたけれ」と唸らせたのも頷ける。『錦の舞衣』を明治期翻訳・翻案文学の頂点の一つとまで言っても、それほど大袈裟とはいえないだろう。
現代人の鑑賞に十二分に耐え得る『錦の舞衣』

翻案が大流行していた
落語でこんな暗い話なのはちょっとどうか、と違和感を感じる向きもあろうが、現在我々が認識しているお笑いとしての落語は、落語の中の1つのジャンルに過ぎない。例えば歌丸師匠が真夏に演じ、ファンを震え上がらせている怪談噺『真景累が淵』(これも円朝作)も立派な高座の「噺」であるし、明治期は長編のストーリーを十数日もかけて語る噺が大いに人気を博していたのだった。
また円朝は極めて進取の気性に富んでおり、盛んに西洋のサスペンス味の濃い小説や戯曲をもとにした作品を演じている。『名人長二』はやはり桜痴に筋を教わったモーパッサン『子殺し』が原作だし、サスペンスもの『黄薔薇(こうしょうび)』、『松乃操美人の生埋(いきうめ)』(これは不注意な古本屋さんの目録などで非常にしばしば『松乃操美人の生理』と誤植され、筆者もしばらく美人の妊娠をめぐる昼メロみたいな作品なのかと思っていた)、歴史もの『英国孝子ジョージ・スミスの伝』など極めて多彩だ。

そういった一連の翻案ものの中でも『錦の舞衣』は、翻案臭をまったく感じさせぬ筋運び、『ラ・トスカ』からの換骨奪胎ぶりの巧緻、登場人物の心の襞にまで入り込んだ心理描写の妙(それもちゃんとヨーロッパ人のマインドから江戸の日本人のマインドへと、違和感なく完璧に落としこまれている凄さ!)、人物造型の見事さ(お須賀のキャラも単なる引き写しでない、オリジナリティーに満ちた造型がなされている)などから、円朝翻案噺の最高傑作といえるだろう。
10年近く前、柳家喬太郎師匠が『錦の舞衣』を演じ、大いに話題になったが(残念ながら筆者は未見)、この噺は現代人の鑑賞に十二分に耐え得るものであり、我こそはという噺家さんには、是非とも今後、積極的に高座にかけていって頂きたいものである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

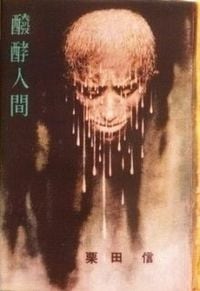





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら