アビガンを共同研究してきた富山大学の白木公康名誉教授(千里金蘭大学副学長)は、開発者という立場上、「自ら発信することにはためらいがある」と話しながらも、中国の論文報告などをもとに、「発症6日までにアビガンを開始すれば、ウイルスの早期消失、咳嗽(せき)の軽減、肺炎の進行や重症化が阻止され、死亡率は激減するはずだ。ウイルス量がピークを過ぎるころから治療を始めても大きな効果は期待できない」と述べる。
白木名誉教授は、「外来の時点で、胸部CTで肺炎を確認して、アビガンを使用して(肺炎の進行を)止めるべきではないか」との考えを示す。
さらに、「アビガンの早期使用は死亡率を下げる効果だけでなく、若い患者が、間質性肺炎による肺の線維化(スポンジのようになり機能しなくなること)や瘢痕化(炎症によって傷跡が残ること)などの後遺症を残さないことにも意味がある」とする。また、「高齢者が急激な悪化を防ぐためにもアビガンは有用」とみている。
催奇形性の影響受ける世代には慎重な投与必要
これだけ聞くとアビガンの早期承認が待たれるが、実際の医療現場で使うとなるには大きな課題がある。白木氏は、早期の段階(無症状や症状の軽い段階)から使えば効果が期待できるとするが、とくに催奇形性の影響を受けやすい世代には、事前に説明して承諾を得なければならない。それは、致死的な症状に陥るかわからない段階で、催奇形性のある薬剤の投与を勧めることを意味する。男性に投与した場合、精液へ移行することがわかっている。
それに備蓄薬としては承認されたが、実際に使われた実績がなく、広く使われた場合にどんな副作用が生じるかは不明だ。承認を得る段階での試験では患者数が限られており、広範囲に使われたときに持病や特異な体質をもつ人にどんな副作用が起きるかは想像がつかない。
アビガンが新型コロナウイルスの救世主になる可能性はあるかもしれない。その一方で、副作用を踏まえたうえでインフォームドコンセントをどうするか、どんな患者にどのように使用するかなど、クリアしなければならない課題は大きい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


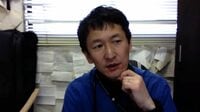






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら