子どもにどんどん読書をさせるべき意外な理由 読書が子どもにもたらす最大の意義とは?
「うちの子は本がすごく好きなのですが、国語が全然できないのはなぜでしょう?」というご質問もあります。
これは多くの場合、「引っかからない」読書の仕方をしていることが原因です。簡単に言うと「読み飛ばしている」のです。
自分がわかる部分だけを読み、読めない漢字や意味のわからない言葉は無視している。読書をしているようでも、なんとなく筋をたどっているだけで、自分なりの考え方でしか文章を読んでいない子どもが多くいるのです。
逆に、国語ができる子どもは実は「引っかかりながら」読んでいます。例えば「主人公は、何で今こんなことを言ったのだろう?」とか「この言葉の意味は、何だろう?」といった具合に。読み方が全然違うのです。
引っかかりながら読めるようにするには?
では、引っかかりながら読めるようにするには、どうすればよいのでしょう。私が、多くの子どもたちの読書を通した「学び方」を見てきた経験から言えることは、保護者の方もその本を読み、子どもと感想を話し合うのが最も効果的だということです。
話し合えば、理解できていない部分や言葉が必ず見えてきますから、「わからないところがあれば聞いてね」とか「こう読むほうが面白いよ」といった言葉をかけつつ、大人と同じように文章から作者の意図をくみ取ろうと考えながら読む感覚に近づける努力を一緒にしてあげることもできます。
なかなか近道はありません。でも、「大人が関わる読書」をすればするほど子どもは着実に正しい読書ができるようになります。
インターネットの普及で、知識を得ることは簡単になりました。知識を得る手段としては、もはや読書は非効率な存在かもしれません。しかし、知識は「経験」になってはじめて身に付きます。
より多くの経験が必要な子どもにとって、「読書」でたくさんの言葉に触れ、時間をかけながら書き手の想いや話の流れを読み取ることで、知識が経験に変わっていきます。心を育む「疑似体験」ができる読書は、単なる机上の学習以上に重要なものだと言えるでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

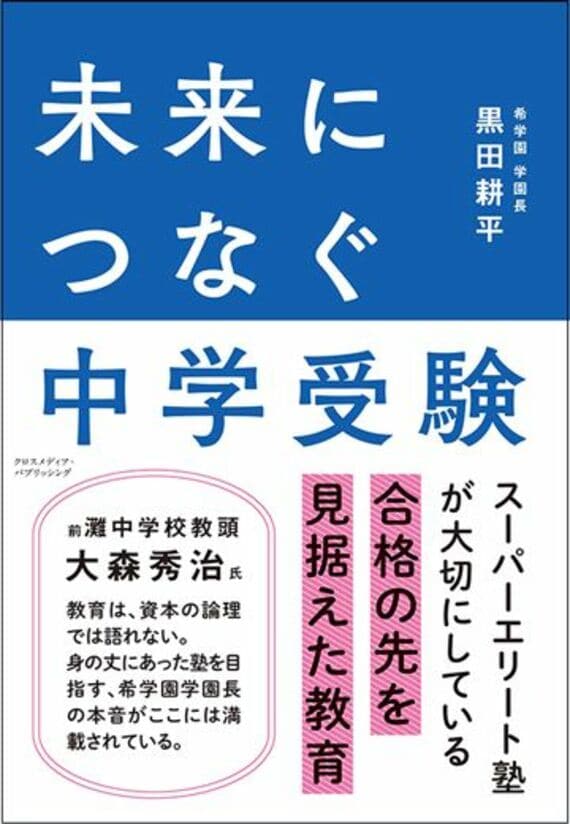
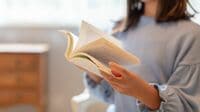





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら