子どもにどんどん読書をさせるべき意外な理由 読書が子どもにもたらす最大の意義とは?
読書には先に述べたとおり、多くの語彙や表現を学ぶことができるという利点もありますが、もう1つ重要なのが読書を通して「疑似体験ができる」という点です。
子どもは生きてきた年数そのものが短いため、実体験を通じて知った事柄も多くありません。もちろん保護者の方が子どもをいろいろな場所に連れて行き、さまざまな実体験を増やす努力をしてもらうことが重要になるのですが、やはり限界があります。
例えば世界各地のことや過去の時代の話、さまざまな人間模様を垣間見るような体験を多く積ませることは、非常に困難です。しかし、そうした事柄も、読書なら実体験に近い「疑似体験」ができます。これこそが、子どもの成長に対して、読書がもたらす最大の意義だと私は考えています。
もちろん情報の入手手段として、テレビやネット動画などの映像もあります。しかし映像で得る情報は、インパクトが強いので瞬間的には印象に残りますが、「眺めている」だけで、実はあまり「頭を使っていない」ということになりがちです。
成長には「経験」が不可欠
読書では、書いてある言葉や登場人物の使うセリフや行動、文脈から正しく情報を読み取り状況把握をすることが求められます。そうやって文字を読むことは手間も時間もかかりますが、頭はフル回転します。
そして自分の頭の中で本に描かれた情景を想像しながら読み進めていくことは、実際に実体験するのと同じぐらい印象にも残りやすいのです。結果、映像よりも断然読書のほうが実体験に近い感覚を得ることができます。
成長には「経験」が不可欠です。経験量が少ないと、未経験のことを想像したり対処したりする力は育ちにくくなります。実体験に勝る経験はありませんが、生きてきた年数が少ない子どもは実体験が少なくて当たり前です。その実体験では間に合わない経験量の不足を、読書を通じた疑似体験が補ってくれるのです。
ただ、ゲームが大好きな今の子どもたちを読書に導くのは本当に至難の業です。そこで保護者の皆さんに心がけていただきたいことは、「子どものロールモデルになる」ことです。
小学生の子どもにとって、親の存在は非常に大きいものです。子どもに読書をさせたいと思えば、親が読書を楽しんでいる姿を見せましょう。親が読書をしないのに子どもだけが読書に目を向けるわけがありません。
さらに重要なことは、「親は子育てだけを精いっぱいしていればいいわけではない」ということです。もちろん子育てはおろそかにするべきことではありませんし、非常に大切なことです。
ただ、子育て以外の何かに本当に熱心に打ち込んでいる姿を子どもに見せる機会を作ってほしいのです。子どもはその姿に憧れを抱くことで、「お父さん、お母さんのようになりたい」と思います。
具体的に、どのような本を読ませればいいのかについてもご紹介しておきます。
希学園で低学年の子どもたちを教えている講師は、10冊の本を読ませるとしたら、7冊は「好きな本」を読ませ、2冊は「もう少し成長したら読めるような本」にし、そして残りの1冊は「まったく子どもが興味を持っていない別ジャンルの本」にしましょう、とアドバイスしています。
10のうち1くらいなら、興味がない本も抵抗感なく読んでくれるものです。そんなバランスで本を読ませていけば、読書を通じて子どもの世界を少しずつ広げられるはずです。

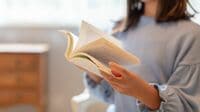





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら